「ねぇ、夏休みの宿題やったの?」
毎年夏になると、この言葉を何回言ってしまうんだろう…と頭を抱えているパパさん、ママさん。本当にお疲れ様です。
僕自身、小学生の頃は宿題をギリギリまで溜め込むタイプでした。8月31日の夜、泣きながら読書感想文を書いていたあの絶望感は、38歳になった今でも忘れられません。
だからこそ、自分の子供たちには「夏休みの後半を、心から笑顔で過ごしてほしい」。
そんな想いから、我が家では数年前から中小企業診断士の学習で身につけた「PDCAサイクル」を応用した宿題管理術を導入しています。
この記事では、「早くやりなさい!」と叱るのをやめて、親が「監督」、子供が「選手」になることで、子供の自主性を引き出し、7月中に宿題を終わらせる我が家の具体的な方法を全てお見せします。
悪夢の再来はさせない!僕が「宿題ハック」を始めたたった1つの理由
8月31日の絶望感…僕自身の苦い原体験
全ての始まりは、僕自身の苦い体験です。夏休みの終盤、テレビから流れる夏の終わりの音楽を聞きながら、「あぁ、もっと計画的にやっておけば…」と後悔する。あの嫌な気分を、我が子には絶対に味わわせたくありませんでした。
妻も「宿題は早めに終わらせる」という考えで一致していたので、上の子が小学校に入学したその年から、我が家の挑戦は始まりました。
「夏休み後半を笑顔で過ごす」が我が家のゴール
僕たちが親子で最初に確認したのは、「何のために宿題を早く終わらせるのか?」という目的(ゴール)です。
それは「夏休みの後半を、思いっきり楽しむため」。
この共通のゴールがあるから、子供たちも「やらされる」のではなく、「楽しむためにやる」というポジティブな気持ちで宿題に向き合えるようになりました。
親は監督、子は選手。我が家の「宿題PDCA」3つのステップ
では、具体的な方法です。我が家では、宿題を親子で乗り越えるためのプロジェクトと捉え、以下の3ステップで進めています。
【Plan】まず敵を知る!宿題の「リストアップ」と「作戦会議」
夏休みが始まったら、まず最初にやるのが「宿題の全体像の把握」です。
- 宿題リストアップ: 配られたプリント類を全部出して、何がどれくらいあるのかを親子で一緒にリストアップします。
- 作戦会議: リストを見ながら、「どれから片付けるか」を子供自身に決めさせます。
僕から「計算ドリルみたいな単純作業は先に終わらせて、自由研究みたいな考える系は後に回したらどう?」と提案はしますが、最終決定は子供に委ねます。 自分で決めることが、当事者意識を持つための第一歩です。
【Do】主役は子供。親は「口出し」より「壁打ち」に徹する
計画が決まったら、あとは実行あるのみ。ここで親がやるべきは、手や口を出すことではなく、子供の「壁打ち」相手になることです。
計画通りに進まない日も当然あります。「友達とプールに行く約束しちゃった!」なんてことも。 そんな時こそ、親の出番です。
「OK!じゃあ、今日のドリルはいつやろうか?明日の午前中?」
こうやって一緒に相談しながら、軌道修正していく。親はあくまで、子供が自走するためのサポート役(マネージャー)に徹します。
【Check & Action】計画通りにいかなくてOK!「どうする?」で育む調整力
週に1回などタイミングを決めて、計画と進捗を一緒に確認します。
大切なのは、できていないことを責めるのではなく、「どうすればうまくいくか?」を一緒に考えること。この小さな「Check」と「Action」の繰り返しが、子供の中に計画性や調整力を育てていくのだと感じています。
「なぜ宿題をやるのか?」腹落ちがやる気をブーストする
今年から特に意識しているのが、「そもそも、なんで宿題ってやらなきゃいけないの?」という根本的な問いに、親子で向き合うことです。
「復習」と「習慣」のため。子供の言葉で伝える大切さ
以前は、僕も「とにかくやるんだ!」と、宿題を単なるタスクとして捉えていました。でも今年から、作戦会議の時に少し時間をとって、息子と「そもそも、なんで宿題ってあるんだろう?」という話を真正面からしてみたんです。
僕は息子にこう伝えました。 「夏休みの宿題はね、スポーツの練習と似てるんだ。一度覚えた技も、練習しないと忘れちゃうだろ?あれが『復習』。そして、毎日体を動かしてないと、いざ試合の時に動けない。勉強も同じで、頭を使うリズムをなくさないための準備運動が『習慣』なんだよ」と。
そして、「だからこれは、先生に言われたからやる『作業』じゃなくて、2学期に最高のスタートを切るための『自分のための準備』なんだ」と付け加えました。
これを伝えてから、息子の言葉が少し変わったんです。「今日のノルマは?」ではなく、「今日はこの復習を終わらせる」と口にするようになりました。やらされ仕事が、自分のミッションに変わった瞬間でした。
苦手な漢字も「未来の自分への投資」と捉える声かけ
とはいえ、一番の壁は息子の苦手な「漢字」でした。「えー、また漢字ぃ?」と机に突っ伏す息子に、どうやってやる気を出させるか。
ここでも役立ったのが、目的の言語化です。僕が診断士の勉強でやっているように、一度解いて間違えたら消して何度も繰り返す、という泥臭いやり方を教えながら 、こんな話をしました。
「今の漢字練習は、ゲームで言えばレベルアップのための『経験値稼ぎ』みたいなものだよ。今、このちょっと面倒な経験値を稼いでおくと、中学校や高校っていう、もっと面白いステージに進んだ時に、すごく楽に戦えるようになるんだ 。それに、2学期が始まって、みんなが忘れてる難しい漢字をスラスラ書けたら、友達から『お前、すげーな!』って言われると思わない?めちゃくちゃかっこいいよ 」
そして最後に、僕自身の話もしました。 「お父さんも今、診断士の難しい勉強をしてるけど、これを乗り越えたら、もっと家族との時間を楽しくできるって信じてるから頑張れるんだ。苦手なことから逃げないのって、未来の自分への最高のプレゼントなんだよ」
未来を具体的に想像させ、親も一緒に戦っている仲間だと示すこと。それが、今を乗り越える力になるようです。
▼ 我が家の「漢字が楽しくなる」おすすめドリル
とはいえ、苦手な漢字をただ繰り返すのは親子ともに苦行ですよね…。
そこで我が家が今年、秘密兵器として導入し、大成功だったのがこの2冊のドリルです。
・下の子(小2)が夢中!『学習ドリル マインクラフトで学ぶかん字』
特にゲーム好きな下の子にハマったのがこれでした。大好きなマイクラの世界観で、アイテムやキャラクターに関連した例文で漢字を学ぶので、もう大盛り上がり。「勉強」というより「冒険の書」を読み解く感覚で、自らペンを走らせていました。
・もはや鉄板!『うんこ漢字ドリル 小学1−6年生の全漢字』
そして、言わずと知れた名作がこちら。上の子も下の子も、例文を読んでケラケラ笑いながら取り組んでいます。「笑い」と結びつくからか、記憶への定着も良い気がしますね。一冊で全学年の漢字を網羅しているので、長く使えてコスパが良いのも親としては嬉しいポイントです。
お子さんの「好き」に合わせて選んであげると、苦手な漢字学習が楽しいイベントに変わるかもしれません。
叱るより効果絶大!「できたこと」を具体的に承認する
子供のやる気を引き出す上で、一番効果があったのが「褒め方」の工夫です。
「すごいね」より「この漢字、覚えられたね!」
子供のやる気を引き出す上で、僕自身が最も意識を改めて、そして最も効果があったのが「褒め方」の工夫です。
以前は、僕もつい「わ、できたの!すごいね!」と声をかけていました。これは子供を**「評価」**する言葉です。「すごい」のは子供自身なので、もし次にできなかった時、「自分はすごくないんだ…」と自信を失うリスクを孕んでいます。
でも今は、「お、この難しい漢字、ちゃんと覚えられたんだね!」というように、具体的にできた「事実」を承認するようにしています。これは、子供の「行動や努力」に焦点を当てた言葉です。「このやり方で頑張れば、できるようになるんだ」と、子供は再現性のある手応えを感じることができます。
この声かけに変えてから、息子の反応も変わりました。以前は「えへへ」と照れるだけだったのが、具体的に褒めるようになってからは、「うん、ここのハネの部分を覚えるのが大変だったんだ」と、自分の頑張りを言語化してくれるようになったのです。
これは、他者からの評価を待つのではなく、自分自身の努力を客観的に認められるようになる、自己肯定感が育つための大切な一歩だと感じています。
自信が次のやる気を生む「好循環」の作り方
「自分は計画通りに宿題を終わらせることができた」という夏休みの終わりに得られる達成感。この小さな成功体験が、雪だるま式に大きくなる「自信」の核になります。
一度、「自分にはできるんだ」という感覚を掴むと、子供の意識は「やらされる宿題」から「自分で管理するプロジェクト」へと変わります。 その自信がつけば、親が「宿題やったの?」と口うるさく言わなくても、来年、再来年と自分で計画を立てて走り出してくれるのです。
そして、この好循環は兄から弟へと伝播します。
弟は、兄が計画的に宿題を終わらせて、夏休み後半を思いっきり楽しんでいる姿をずっと見ています。 だから彼にとって、「宿題は早く終わらせるのが当たり前で、その方がカッコいい」のです。 僕がガミガミ言わなくても、最高のロールモデルがすぐ隣にいるのですから。
子供たちがこうして自信をつけていく姿は、僕自身の挑戦への大きな励みにもなっています。彼らが自分の力で課題を乗り越えるのを見るたびに、「よし、僕も診断士の勉強、頑張ろう」と、逆に背中を押されるのです。
まとめ:完璧じゃなくていい。我が家だけの「作戦」を見つける夏へ
夏休みの宿題は、親子のバトルになりがちです。でも、親が少しだけ関わり方を変えることで、子供の自主性を育む絶好の機会に変えることができます。
もちろん、この記事でお話ししたのは、あくまで我が家の一事例です。ご家庭の状況やお子さんの性格によって、合う合わないは必ずあります。
だから、最初から完璧にやろうなんて思わなくて大丈夫です。たとえ計画が3日坊主で終わっても、それは決して失敗ではありません。「どうすればできるかな?」と親子で一緒に頭を悩ませた時間こそが、来年につながる最高の財産になります。
もしかしたら、この話の本当のゴールは、宿題をきっちり終わらせることではなく、「宿題やったの?」という監視の言葉を、「宿題、どんな感じ?」という対話の言葉に変える、たったそれだけなのかもしれません。
今年の夏は、まずはお子さんと一緒に「作戦会議」を開いて、ご自身の家族だけのオリジナルな一歩を踏み出してみませんか?
きっと、親のイライラが少しだけ軽くなり、子供がほんの少しだけたくましく見える、新しい夏が待っているはずです。





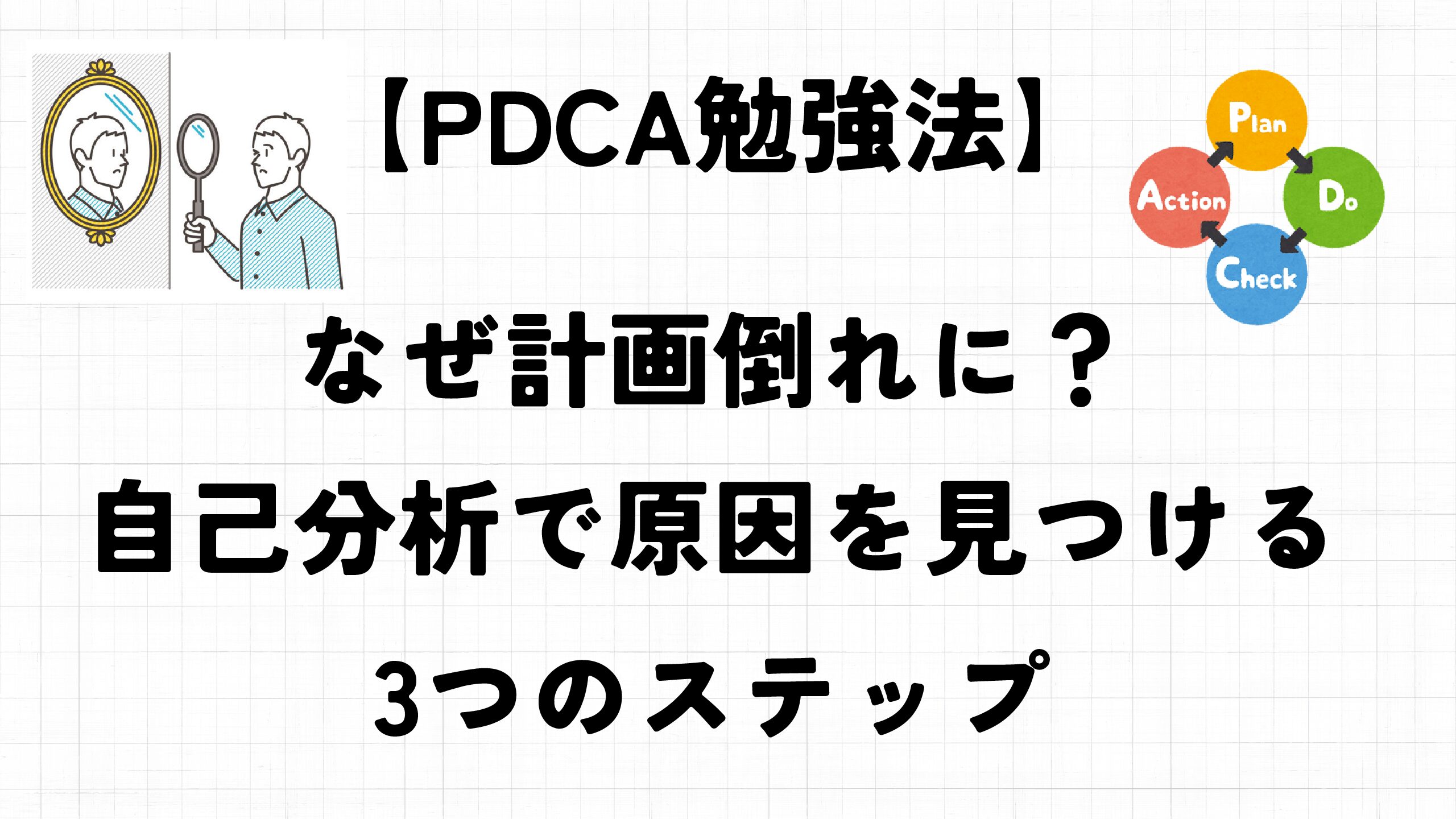
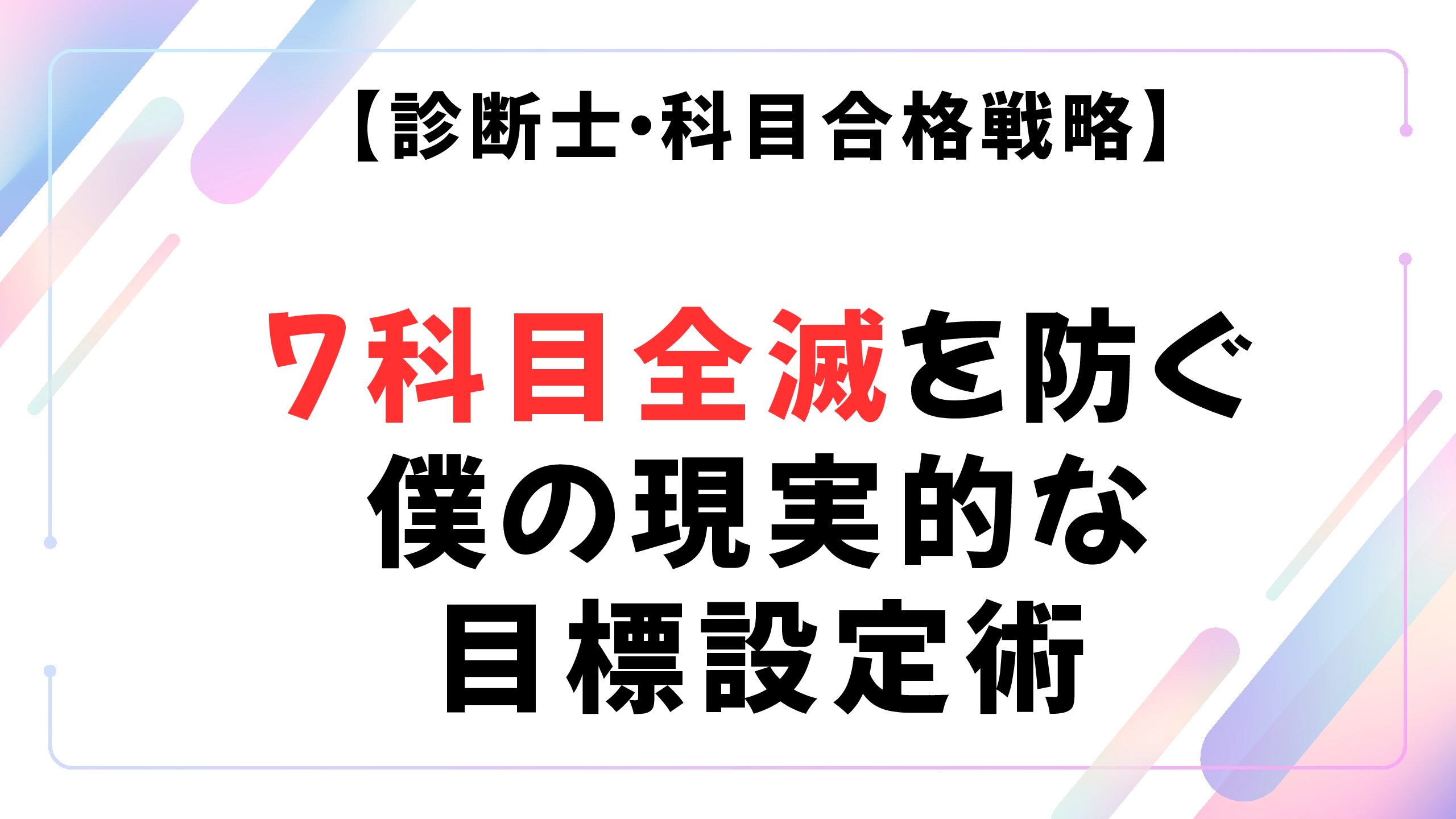
コメント