-

【中小企業診断士・決定版】5年の遠回りを凝縮。独学の努力を成果に変える『AI勉強法の教科書』
-

【完全マニュアル】独学の努力をあなたに最適化する。『ログシバ式 学習OS』の全構築手順
-

5年遠回りした「学習OS」の”心臓部”は、AIプロンプトだった。あなたの『分かったつもり』を破壊する「ログシバ式・学習OSプロンプト」【お試し版/完全版比較】
-

【2026年合格目標】5年目の凡人が追加投資5.5万円で挑む、診断士合格への全戦略
-

【診断士受験生へ】NotebookLMを知らないと損!僕の学習効率が5倍になった「学習OS」構築術
-

『これ、紙の方が速いじゃん…』- 僕がiPad miniでの大失敗から見つけた、最高の自己投資としてのiPad Pro/Air
【診断士・科目合格戦略】7科目全滅を防ぐ、僕の現実的な目標設定術
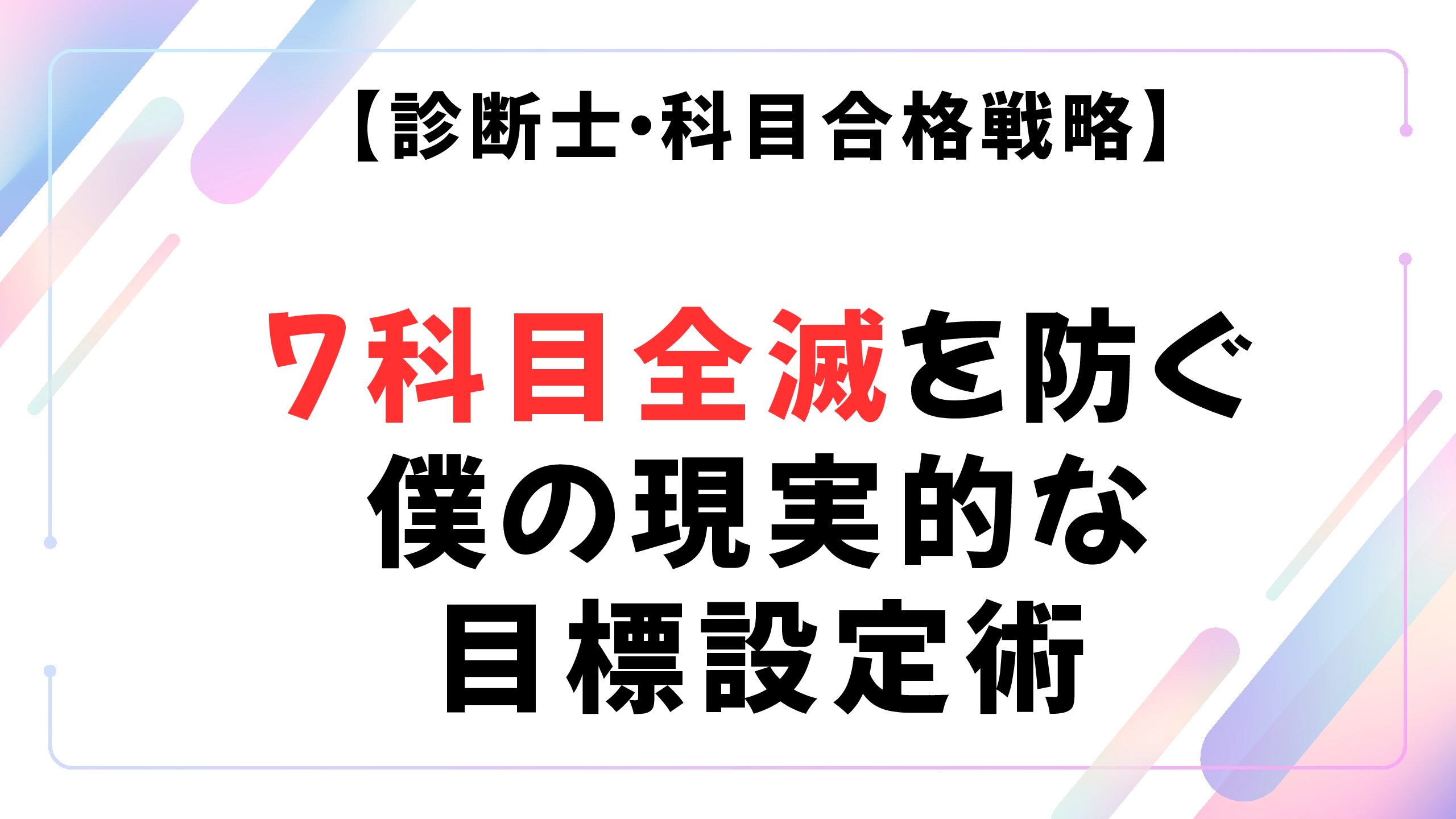
【序章】これは、僕が「一発合格」という呪いを捨てた日の記録です
「中小企業診断士になるなら、7科目一発合格が理想だ」
その言葉は、挑戦者にとって、輝かしい勲章のように見えます。
もちろん、数ヶ月前の僕も、その光に向かってがむしゃらに走っていました。
しかし、その「完璧な理想」は、 時間のない社会人にとっては、時に自分自身を、 そして、最も大切な家族を傷つける、危険な「呪い」に変わることを、僕はまだ知りませんでした。
2025年の一次試験。 僕の「財務・会計」の点数は、28点でした。
普通なら、絶望に打ちひしがれ、全てを諦めてしまう点数です。
しかし、僕は不思議なほど晴れやかな気持ちで、 次の一歩を見据えています。
なぜならこれは、僕の「失敗」の記録ではないからです。
僕が、僕の人生にとって本当に大切なものを守るために、 「一発合格」という呪いを自らの手で解き放ち、 「戦略的勝利」への道を歩み始めた、その第一歩の記録なのです。
この記事は、僕がなぜ輝かしい道を捨て、 「科目合格」という泥臭い、しかし確実な戦略を選んだのか。 その葛藤と決意、そして手に入れた本当の力の全てを記した、僕の航海日誌です。
もしあなたが、僕と同じように「合格」という目標と、 人生の他の大切なものとの間で揺れているのなら。
この、僕のリアルな試行錯誤の全記録が、 あなたが「あなただけの最善の道」を見つけるための、小さな光になることを願っています。
(※ちなみに、この絶望的な点数から、いかにして2科目の合格を掴み取り、次なる戦いへと繋げたのか。その具体的な逆襲の物語は、こちらの記事に綴りました)
▼参考記事:
【奮闘の軌跡】逆襲編:24点からの「戦略的勝利」
第1章:僕の勉強が、家族の笑顔を曇らせてしまった、ある夜の話
仕事、家事、育児、そして、深夜に始まる孤独な勉強。
全てを完璧にこなそうとするうちに、僕の心のコップは、自分でも気づかないうちに、完全に干上がっていました。
資格勉強と家族との両立という、あまりにも高い壁。 その前で、僕は完全に道を見失っていたのです。
そんなある日の夜でした。
些細なことがきっかけで、妻と気持ちがすれ違い、空気が重くなったとき。 僕は、妻の悲しそうな顔を見て、ハッとしました。
「ああ、またやってしまった…」
僕の頭の中は、常に勉強のことでいっぱいでした。
子供の「ねぇ、これ見て!」という無邪気な声に、心からの笑顔で応えられない自分。 妻の何気ない一言に、焦りから不機嫌な態度で返してしまう自分。
僕の焦りが、一番大切なはずの家族の笑顔を、曇らせてしまっている。
そのどうしようもない事実に、僕は打ちのめされました。
未来の家族の幸せのための勉強が、目の前にある家族の「今」を犠牲にしては、本末転倒だ。
僕が今すぐ向き合うべきは、分厚い参考書ではなく、目の前にいる家族の心だと、痛いほど痛感しました。
(その時の、もっと詳しい心境や出来事、妻とのやり取りについては、こちらの『決意編』で、僕の弱さも全て、赤裸々に告白しています)
だから、僕は決めました。 重く、しかし、あまりにも当たり前の決断を。
今年の「7科目一発合格」という目標を、一旦、手放します、と。
これは、夢を諦めるための「挫折」ではありません。
僕の人生の土台である家族との時間を何よりも大切にし、万全の状態で再びこの大きな山に挑戦するための、前向きな「戦略的撤退」なのです。
第2章:僕の決断を「挫折」から「戦略」に変えてくれた、一筋の光
「一発合格」という、大きな目標を手放した、あの夜。
正直に言えば、僕の心の中には、 安堵と共に、一つの消せない不安がありました。
「本当に、これでよかったのだろうか…?」
夢から逃げ出した、ただの敗者なのではないか。
そんな自己嫌悪の暗闇の中で、 僕はある一つの「光」を見つけます。
それが、中小企業診断士試験が、 僕たち社会人受験生のために用意してくれていた、 「科目合格」という制度でした。
これは「救済措置」ではない。「賢者の道」だ
これは、7科目のうち60点以上で合格した科目は、 その後2年間、その科目の受験が免除されるというもの。
つまり、最大3年間かけて7科目を揃えれば、 1次試験を突破できる、という仕組みです。 (※詳しくは、中小企業診断協会の公式サイトでも定められています)
多くの人は、これを単なる「救済措置」だと考えているかもしれません。
しかし、僕にはそうは見えませんでした。
仕事や家庭と両立しながら、この難関に挑む、すべての社会人。 その限られたリソースをどう配分し、 どうすれば確実に勝利を掴めるか。
これは、試験制度が僕たちに突きつけている、 問いそのものであり、「戦略」なのだと、僕は気づいたのです。
全てを賭けて全滅するリスクを冒す「博打(ばくち)の道」ではなく、
目の前の勝利を一つひとつ、 確実に積み重ねていく「賢者の道」。
僕の決断は、間違いではなかった。
この制度こそが、僕の選んだ道を肯定してくれる、 何よりの証拠でした。
第3章:「7科目」という呪いを捨てて、僕が手に入れた4つの本当の力
「科目合格」という、賢者の道。
この戦略に切り替えたことで、 僕の勉強の質、そして心のあり方は、 自分でも驚くほど、劇的に変わりました。
それは、 「7科目一発合格」という重い鎖から、 ようやく解放された、瞬間でした。
力①:「焦り」が「集中」に変わった、精神的な余裕
【Before】
かつての僕は、「全部やらなきゃ」という強迫観念に、 常に追い立てられていました。
財務会計の勉強をしていても、 頭の片隅では「ああ、経営法務もやらなきゃ…」と焦っている。
これでは、目の前の知識が身につくはずもありませんでした。
【After】
しかし今、僕の心は、驚くほど穏やかです。
「今年は、この2科目を獲る」その明確で、達成可能な目標があるから。
目の前の1科目に、 自分の持てる全てのエネルギーを注ぎ込める。
この「一点集中」できる環境こそが、 学習効率を最大化する上で、何よりも重要な力でした。
力②:「自己嫌悪」が「自信」に変わった、計画の確実性
【Before】
無謀な7科目計画は、毎日「未達」を生み出しました。
「今日も計画通りにやれなかった…」
その小さな自己嫌悪の積み重ねが、僕の学習意欲を静かに殺していきました。
【After】
学習計画がシンプルになったことで、計画通りに遂行できる日が、劇的に増えました。
「今日も、決めたことはやり切れた」。
この小さな成功体験の積み重ねが、「やればできる」という確かな自信に変わっていきます。
そもそも、なぜ僕たちの計画は倒れてしまうのか。
その根本原因と、自分に合った計画を立てるための具体的な自己分析の方法は、こちらの記事で深掘りしています。
▼参考記事
【PDCA勉強法】なぜ計画倒れに?自己分析で原因を見つける3つのステップ
力③:「不安」が「手応え」に変わった、勝利の方程式
【Before】
「このやり方で、本当に合格できるのか…?」
5年間、僕は常にこの漠然とした不安と戦っていました。
【After】
2科目に絞って合格できたという成功体験は、 僕に何より大きなものをもたらしてくれました。
それは、 「このやり方なら、自分は勝てる」という、僕が『ログシバ式 学習OS』の原点であり、「来年こそは残りの科目も獲れる」という、揺るぎない自信に繋がっています。このOSの具体的な構築方法は、以下の記事でその全てを解説しています。
▼参考記事:
【完全マニュアル】独学の努力を100%結果に変える。『ログシバ式 学習OS』の全構築手順
力④:「消耗戦」が「戦略戦」に変わった、本番での優位性
【Before】
7科目全てで合格点を狙うのは、 試験当日の2日間を、全力疾走で駆け抜けるようなものです。
後半の科目では、体力も集中力も限界でした。
【After】
本番の試験で、捨て科目は雰囲気をつかむことに徹し、早めに退出できる。
他の受験生が必死になっているその時間を、 最後の本命科目のための、最終確認と精神統一の時間に充てられる。
試験本番という最も重要な局面で、 ライバルに対して圧倒的な「時間的・精神的アドバンテージ」を手にすることができる。
これもまた、この戦略がもたらす、計り知れない力なのです。
第4章:僕の「勝利の設計図」- 3つの戦略的思考プロセス
では、具体的にどうやって中小企業診断士の勉強計画を立てるのか。 僕が、あの決意の夜から、実際にペンを取り、自分だけの「勝利の設計図」を描き上げるまでの、頭の中の思考プロセスを、全て公開します。
思考①:「希望」ではなく「現実」からスタートする
まず、僕がやったこと。
それは、「もしかしたら、1日3時間くらい勉強できるかも…」という、淡い希望を、全て捨てることでした。
自分の1週間のスケジュールを冷徹に見つめ、絶対に動かせない「仕事」「育児」「家族との時間」を先に塗りつぶしていく。
そして、残された本当に僅かな時間。 それが、僕が使える「現実」です。
多くの計画が失敗するのは、「理想」からスタートするからです。
そうではなく、冷徹な「現実」を直視し、「今の自分にできること」と「できないこと」を明確に分ける。
そして、できないことは「やらない」と覚悟を決めること。 それが、全てのスタートラインでした。
思考②:「ゴール」から逆算し、あえて”王様”を捨てる
これが、僕の戦略の心臓部です。
僕は、「2次試験との関連性が高い主要科目」を、初年度のターゲットから、戦略的に「捨てる」ことに決めました。
具体的には「財務・会計」「企業経営理論」「運営管理」です。
「え、そこを捨てるの?」と、きっとあなたは思うはずです。
僕も、この決断には勇気がいりました。
しかし、僕の最終ゴールは、「来年、1次試験を突破したその勢いのまま、一気に2次試験まで駆け抜けること」です。
そのためには、2次試験に直結する最も重要な主要科目は、中途半半端な知識ではなく、最も新鮮で、研ぎ澄まされた知識で挑むべきだと考えたのです。
だからこそ、今年は。
単体で知識が完結し、かつ僕が比較的得意だった「経営情報システム」と「中小企業経営・政策」の2科目に全リソースを集中させ、確実に「科目合格」という名の“貯金”を稼ぎにいく。
これが、僕の下した、最も重要な戦略的決断でした。
思考③:「捨てる」とは、「無視する」ことではない
「捨てる」といっても、40点未満の「足切り」は、絶対に避けなければなりません。
そこで僕は、捨て科目については、過去問は一切解かない代わりに、スタディングの講義動画とテキストだけは、必ず一度は通して見る、という最低限のルールを課しました。
これは、合格点を獲るためではありません。
「どんな敵が、どんな武器で待ち構えているのか」という、戦場の雰囲気だけは掴んでおくための、最低限のリスク管理です。
この3つの思考プロセスを経て、僕だけの「勝利の設計図」は完成しました。
それは、決して派手ではありませんが、今の僕が確実に勝利を掴むための、最も現実的な道筋だと、僕は確信しています。
まとめ:「合格」よりも大切な、自分の「生き方」を見つけるということ
あの夜、僕が決意したこと。
それは、単に「7科目合格を諦める」ということではありませんでした。
僕にとって、この挑戦は、いつしか単なる資格取得ではなくなっていました。
長期間、計画的に努力を続けることで、自分の「習慣」を変え、そして自分の「生き方」そのものを見つめ直していくこと。
それこそが、本当の目的なのだと、今では思っています。
社会には、「一発合格こそが正義だ」という、目に見えない圧力が確かに存在します。
でも、僕たちは、誰かが決めた「理想の物差し」で、自分の価値を測る必要なんて、どこにもないのです。
自分自身の人生と、家族と、限りある時間と、真正面から向き合う。
その中で、自分にとっての最善の計画を立て、目の前の「合格」を、一つひとつ、自分の手で確実に掴み取っていく。
遠回りに見えるかもしれません。
しかし、それこそが、僕たち社会人が、 自分自身を、そして、かけがえのない大切な人を守りながら、この大きな山を制覇するための、唯一の、そして最短のルートだと、僕は信じています。
【そして、次のステージへ】あなたの「全体戦略」を、ここから始めよう
この「科目合格」という戦術は、僕の挑戦のほんの一部です。
僕が2026年の合格に向けて立てた、学習スケジュール、投資予算、そして各科目の攻略法まで含めた冒険の「全体地図」は、こちらの記事で公開しています。
あなたが、あなただけの「勝利の設計図」を描くための、最初のヒントがきっと見つかるはずです。
▼参考記事
【2026年合格目標】5年の凡人が追加投資5.5万円で挑む、診断士合格への全戦略
あなたが、あなた自身の大切なものを守るために、「やらない」と決めていることはありますか?
もしよければ、あなたの戦略も、コメントで教えてください。

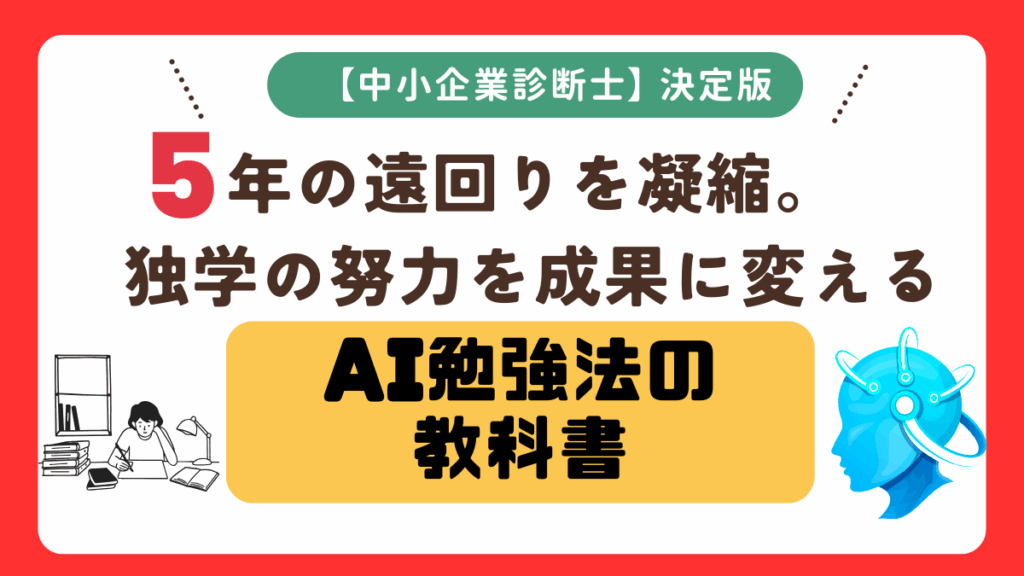
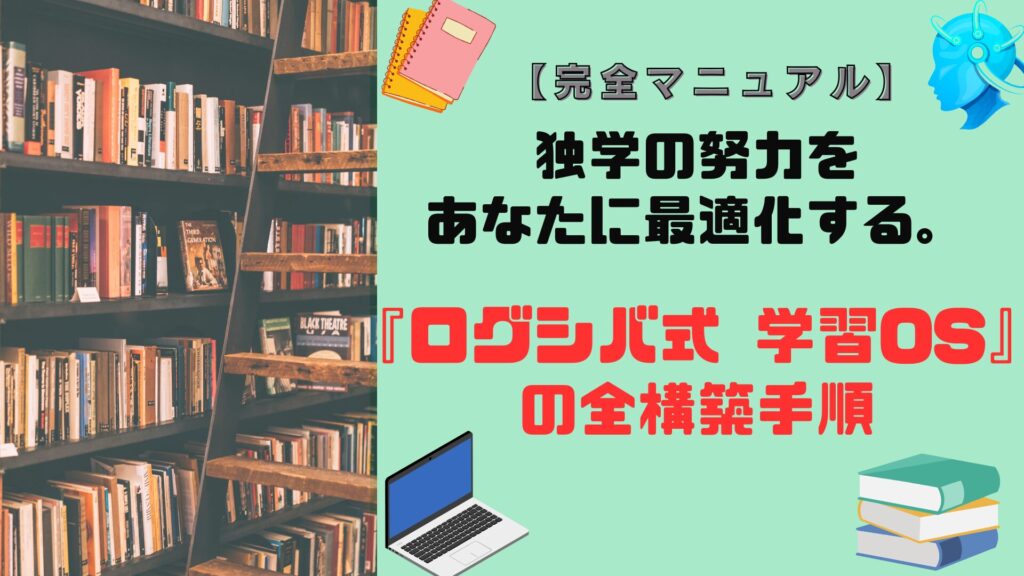
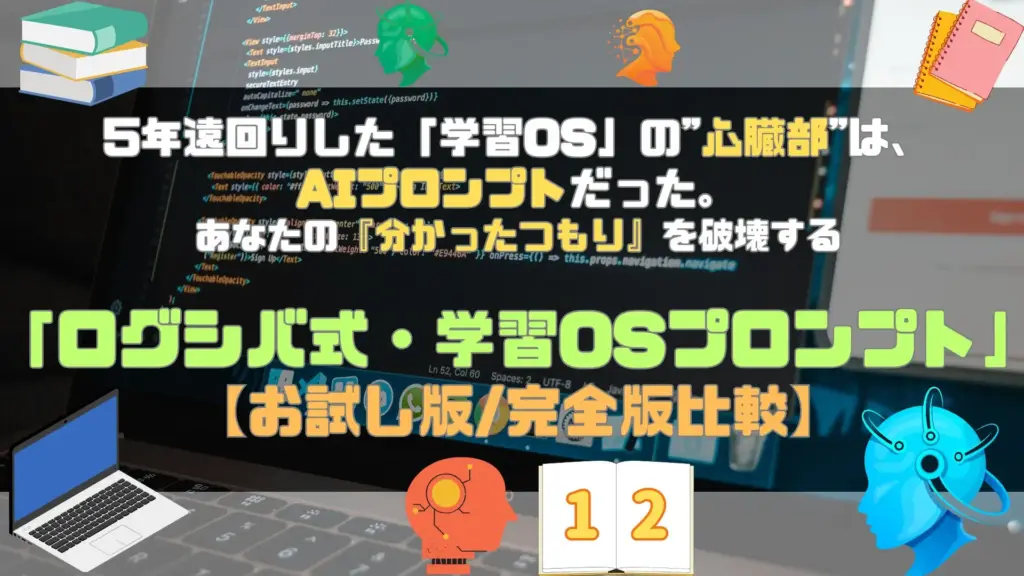
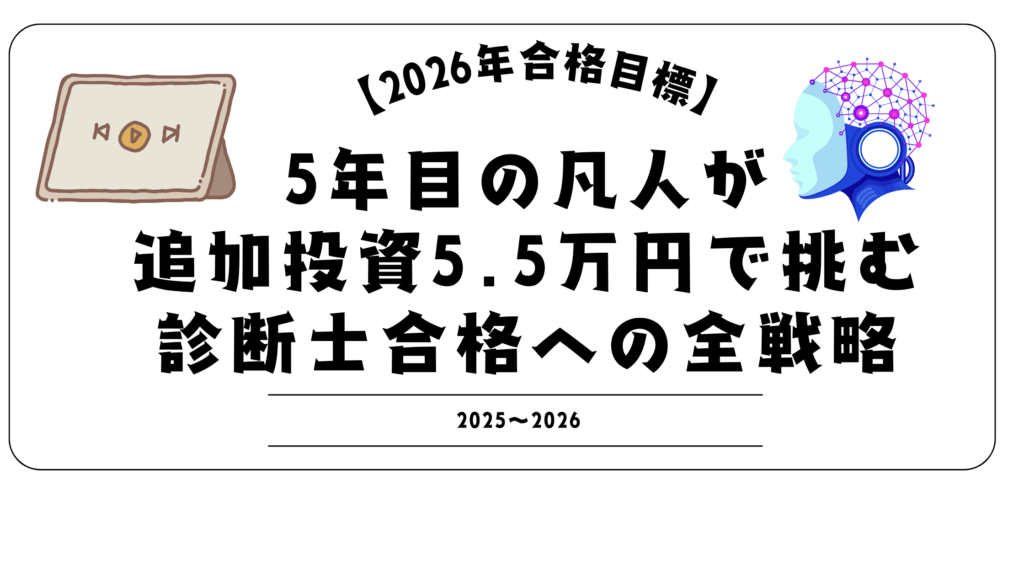
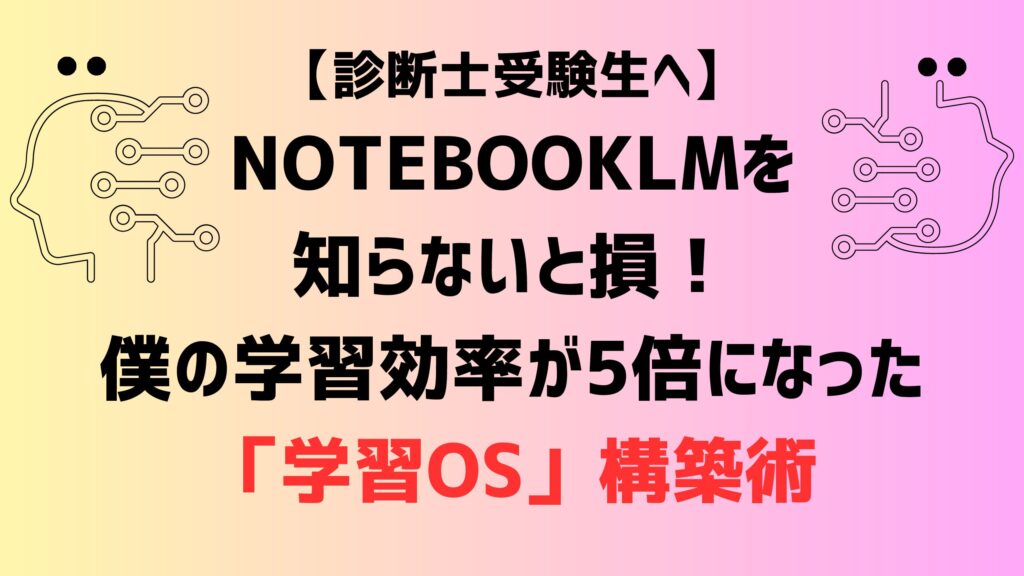
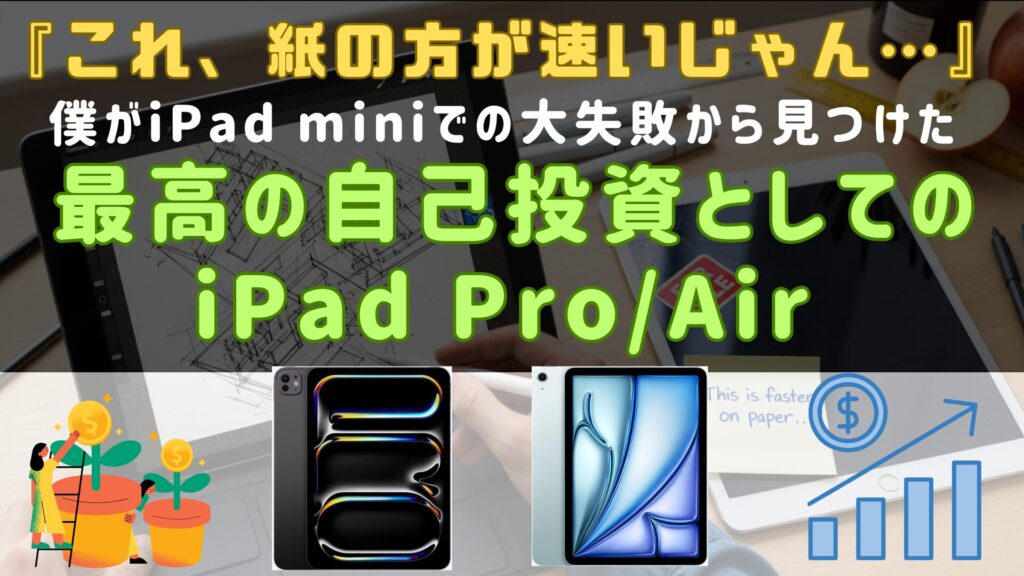
コメント