-

【中小企業診断士・決定版】5年の遠回りを凝縮。独学の努力を成果に変える『AI勉強法の教科書』
-

【完全マニュアル】独学の努力をあなたに最適化する。『ログシバ式 学習OS』の全構築手順
-

5年遠回りした「学習OS」の”心臓部”は、AIプロンプトだった。あなたの『分かったつもり』を破壊する「ログシバ式・学習OSプロンプト」【お試し版/完全版比較】
-

【2026年合格目標】5年目の凡人が追加投資5.5万円で挑む、診断士合格への全戦略
-

【診断士受験生へ】NotebookLMを知らないと損!僕の学習効率が5倍になった「学習OS」構築術
-

『これ、紙の方が速いじゃん…』- 僕がiPad miniでの大失敗から見つけた、最高の自己投資としてのiPad Pro/Air
【学習OS運用ログ Vol.2】なぜ?が腹落ちする。AIの対話で見つけた『腹落ち学習法』の全手順
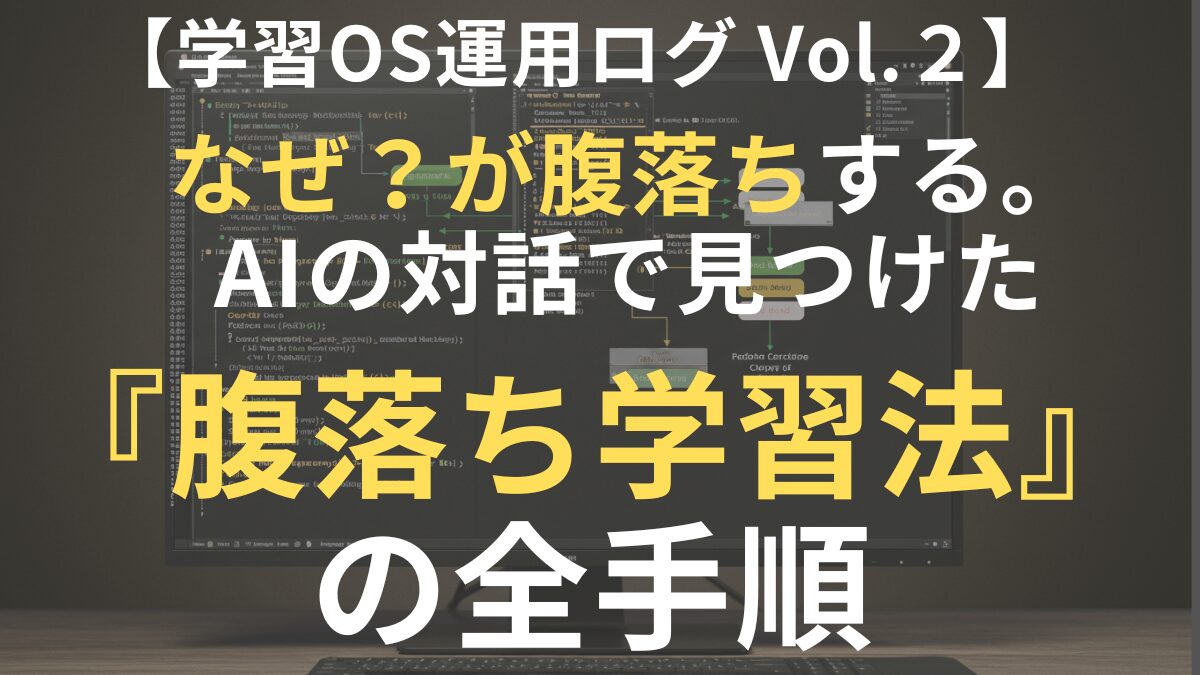
【序章】あの日の誓いと、新たな壁
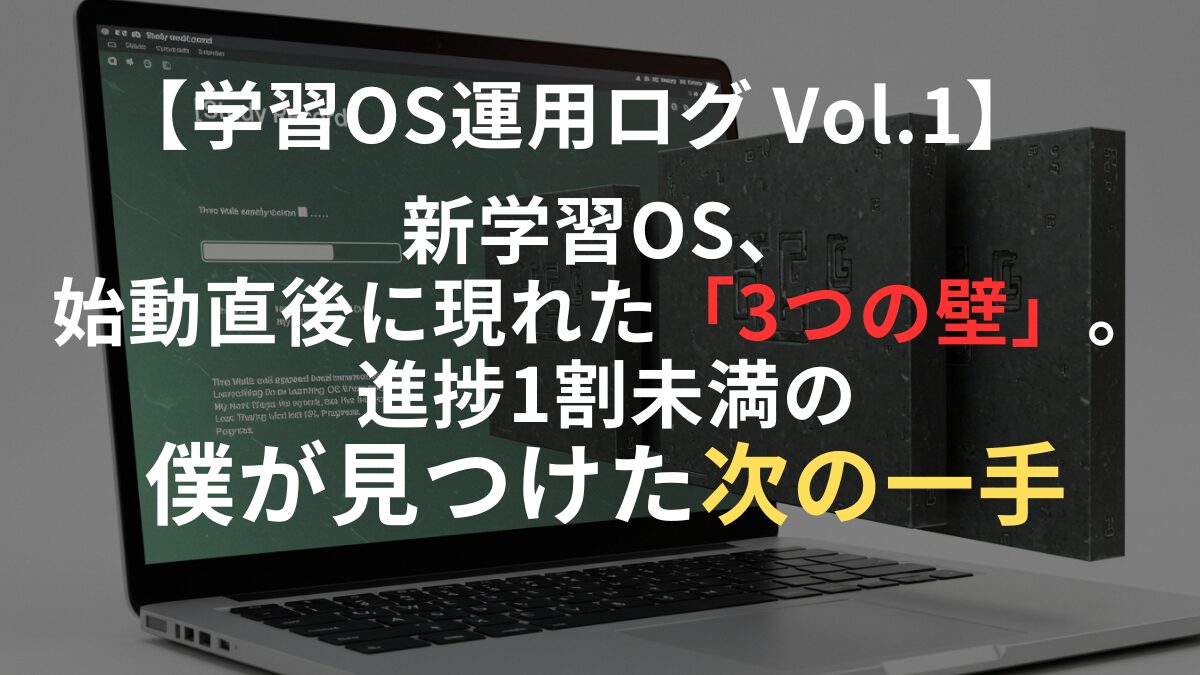
先週の記事で、僕はシステムの不具合や知識不足という「3つの壁」にぶつかりながらも、こう誓いました。
「つまずいている『企業会計の基礎』の単元を、今週中に必ず終わらせる」
しかし、その誓いを実行しようとした僕の前に、またしても新たな壁が立ちはだかりました。それは、「解説を読んでも、心の底から理解できない」という、独学者にとって最も厄介な壁です。
この記事は、そんな僕がたった一問の「分からない問題」と向き合った末に、僕の学習OSをアップデートする『腹落ち学習法』を確立し、ついにその壁を突破した思考のプロセスと、OSを最適化した記録です。
【本章】『腹落ち学習法』の実践プロセス:「売価還元法」を分解する
■令和元年度 第6問
棚卸資産の評価に関する記述として,最も適切なものはどれか。 (選択肢は省略)
今週、僕が対峙していた「財務・会計」の単元。その中でも、この一問が僕を完全に沼らせました。正解は「ウ」なのですが、その選択肢に含まれる「売価還元法」という言葉が、何度読んでも頭に入ってこないのです。
今回、僕が格闘したこの一問は、多くの中小企業診断士受験生が愛用する『中小企業診断士試験 過去問完全マスター 2 財務・会計』に掲載されている問題です。
まさに受験生のバイブルとも言える一冊ですが、今回の発見は、この一冊を「AIと連携させることで、単に問題を解くだけではない、全く新しい血肉の通わせ方ができる」という可能性を示してくれました。
ステップ1:公式解説(過去問マスター)の確認
まずは公式の解説書、「過去問マスター」を読み込みます。
過去問マスターの解説(抜粋)
ウ:適切である。売価還元法 (=値入率等の類似性に基づく…原価率を乗じて…価額とする方法)は,取扱品種の極めて多い小売業等の業種において適用される…
正直に言って、僕には「呪文」にしか見えませんでした。結論は分かる。でも、なぜそうなるのかが腹落ちしない。この「分かったふり」で進むのが、一番危ないと分かっているからこそ、もどかしい時間が過ぎていきました。
ステップ2:AI司書(NotebookLM)による定義の深掘り
次に頼ったのが、自前のPDF教材を読み込ませてあるAI「NotebookLM」です。彼に聞くと、教科書のように正確な答えを返してくれます。
「売価還元法とは、期末商品の売価合計額に原価率を掛けて、原価を推定する方法です」
なるほど。理論の骨子は理解できました。過去問マスターよりはずっと分かりやすい。 でも、まだ「なぜ、そんな面倒なことを?」「小売業で使われる理由は?」という、肝心な部分がイメージできませんでした。
ステップ3:AI家庭教師(Gemini)による具体例での『腹落ち』
最後に投入したのが、幅広い知識を持つ生成AI「Gemini」です。彼には、こう聞きました。
「売価還元法を、コンビニのアルバイトを始めたばかりの高校生にも分かるように教えて」
すると、彼はこう答えてくれました。
「コンビニにはお菓子やジュースが何千個もあって、全部の仕入れ値を調べるのは大変だよね?
でも『大体のお店の利益率は40%』って分かってたらどう?
期末に店に残ってる商品の『定価』を全部足して、それに原価率(60%)をかければ、一個一個調べなくても、ざっくりとした在庫の原価が分かるよね。
これが売価還元法だよ」
ブレークスルー:3つの視点が繋がった瞬間
このGeminiの具体的な例え話を聞いた瞬間、僕の頭の中で、バラバラだった3つの情報がカチッとはまりました。
- Geminiの例え話で、「なぜ小売業で使うのか」という根本的な目的を理解する。
- その上でNotebookLMの正確な定義を読み返し、理論的な裏付けを得る。
- 最後に過去問マスターの難解な文章をもう一度見ると、「ああ、この呪文は、あのコンビニの話を学者っぽく言ってるだけなんだな」と、初めて心の底から理解できたのです。
【最終成果物】僕の学習OSが生み出した「腹落ち」まとめシート
先週の記事で書いた「知識の壁」は、気合や根性だけでは乗り越えられません。でも、こうしてツールの使い方を工夫し、自分なりの攻略法を見つけることで、分厚い壁にも風穴を開けることができる。
その具体的な成果物として、今回の試行錯誤の末に完成した【統合版まとめシート】を、ここに公開します。
【統合版まとめシート】令和元年度 第6問:棚卸資産の評価
1. このテーマの戦略的意義(作戦参謀 by Gemini)
- ランク:B(制度会計の基本。失点はビハインドに直結)
- キーワード:低価法、正味売却価額、評価損=売上原価、売価還元法
- 理論の骨子:企業の期末在庫の価値を、「保守主義の原則」に基づき厳しくチェックするルール。資産の価値が下がった場合は、すぐに損失として認識する。
- 2次試験へのブリッジ:
- 事例Ⅳ:「評価損〇〇円を計上」という指示は「売上原価にプラス!」と即座に反応する。
- 診断士として:評価損が多額な企業は「過剰・滞留在庫」のサイン。「ABC分析」や「需要予測」といった改善策の引き出しに直結する。
2. 各選択肢の徹底解説(家庭教師 by LM)
- ア (不適切): 棚卸資産の期末評価で帳簿価額と比較すべき時価は「正味売却価額」が原則。「再調達原価」はあくまで例外的な代替処理。
- Gemini補足:正味売却価額とは「この在庫、今売ったらいくら手元に残るか?」というリアルな価値。
- イ (不適切): 「個別法」は、宝石や不動産など個別管理できる場合に適用される、正式に認められた評価方法。
- ウ (適切): 「売価還元法」は、スーパーや百貨店など、取扱品目が極めて多く、個々の原価管理が困難な小売業で適用される方法。
- 工 (不適切): 簿価切り下げによる評価損は、通常の販売活動の中で発生するものなので、原則として「売上原価」として処理する。
- Gemini補足:費用収益対応の原則から、売上高と直接対応させるのが合理的。営業外費用や特別損失ではない。
3. 次への一手(両AIより統合)
- 「棚卸資産評価」と見たら、頭の中で「①時価は?→正味売却価額」「②評価損は?→売上原価」「③例外は?→売価還元法」の3点セットを瞬時に展開する癖をつける。
- 「なぜ棚卸資産評価損は売上原価なのか?」を、費用収益対応の原則と結びつけて自分の言葉で説明してみる。
僕の挑戦は、まだ始まったばかりです。


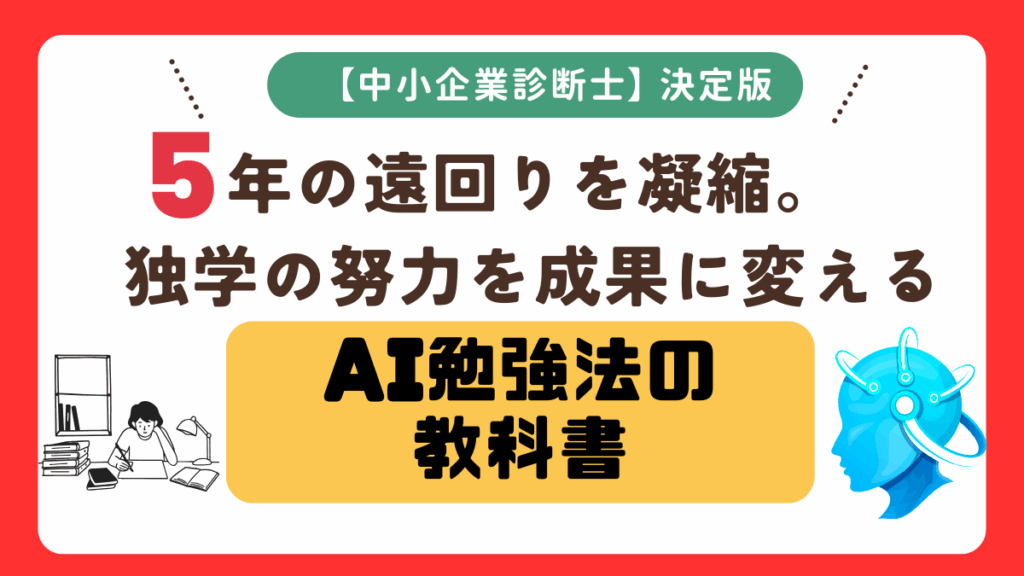
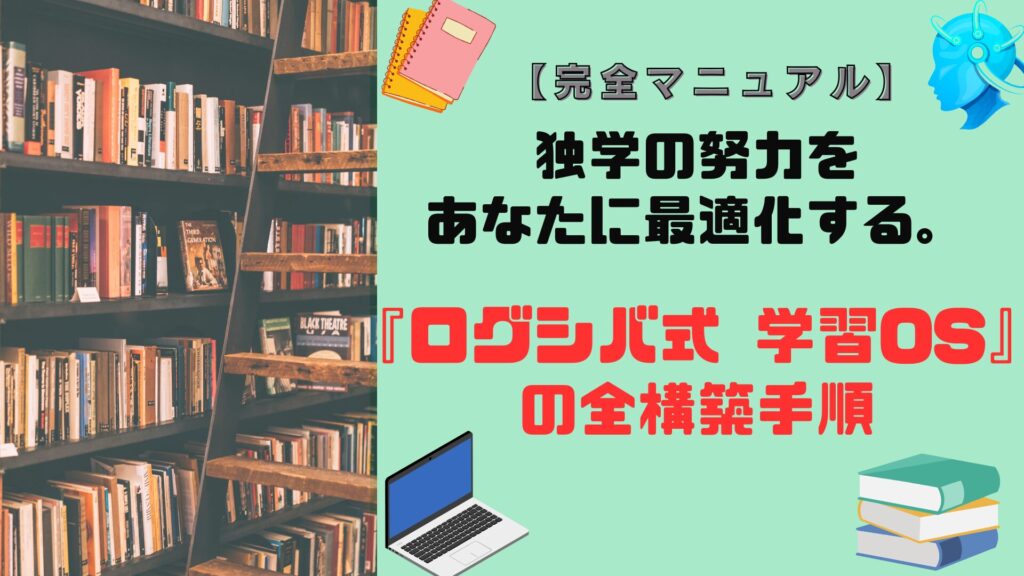
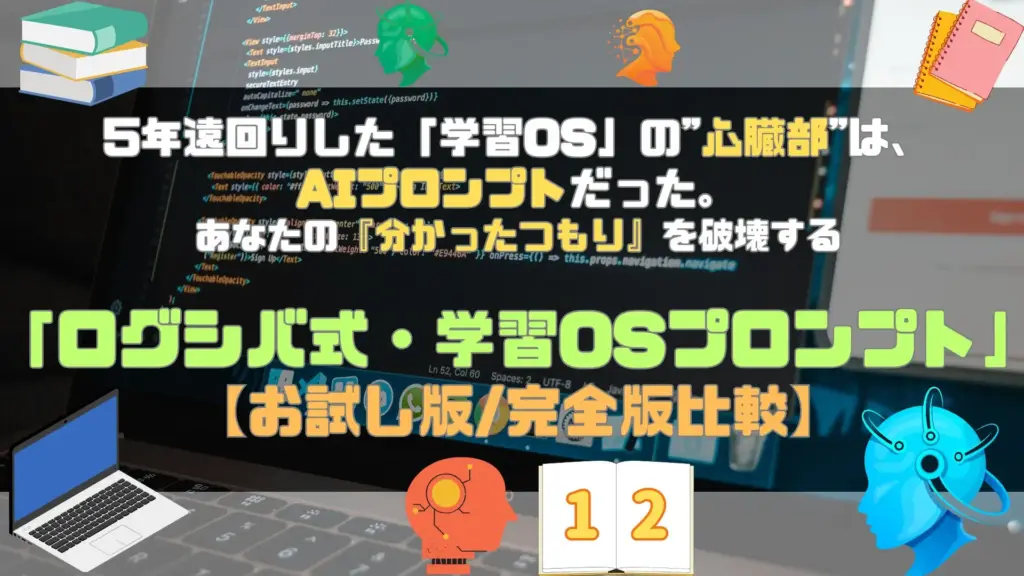
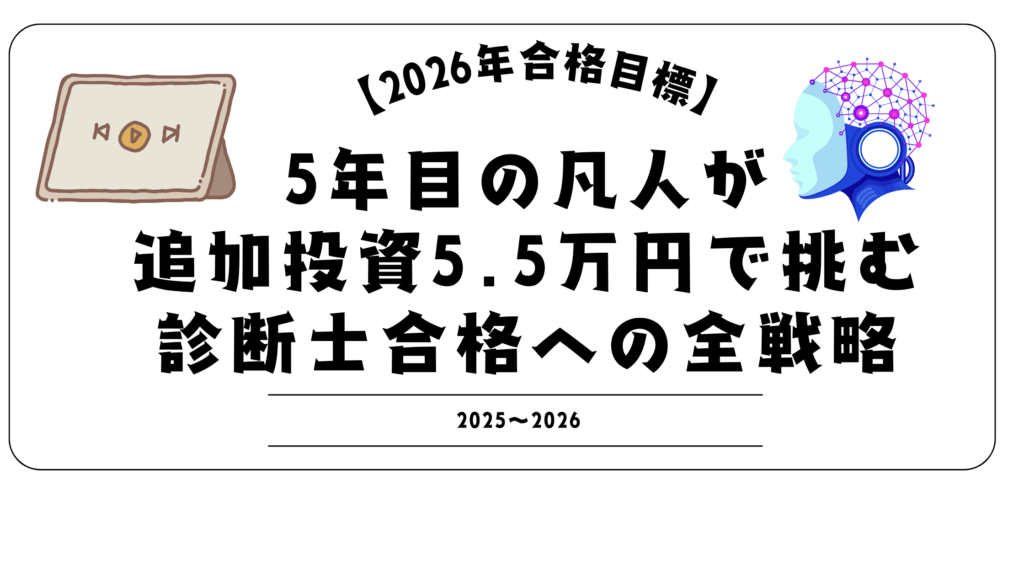
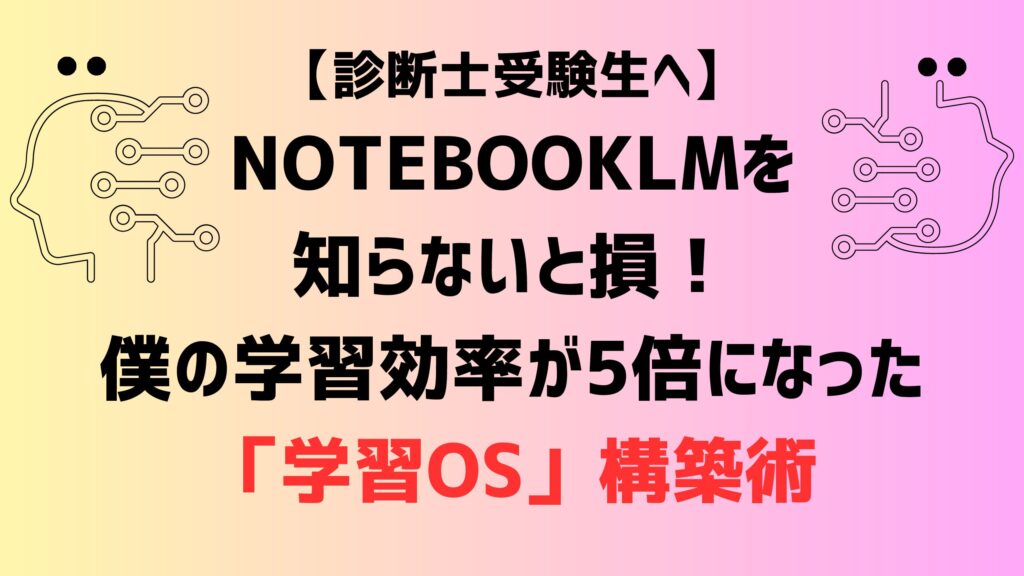
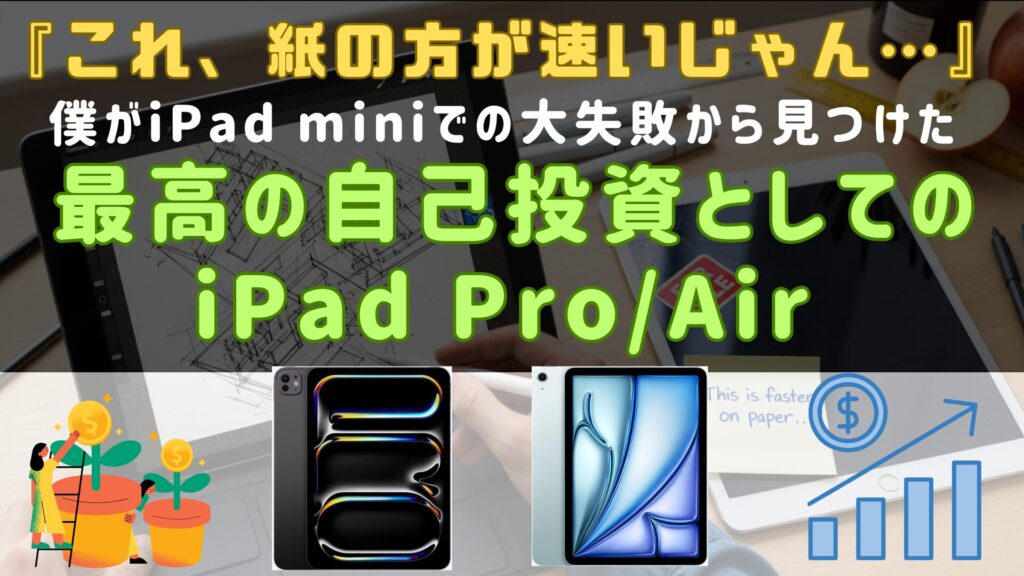

コメント