-

【中小企業診断士・決定版】5年の遠回りを凝縮。独学の努力を成果に変える『AI勉強法の教科書』
-

【完全マニュアル】独学の努力をあなたに最適化する。『ログシバ式 学習OS』の全構築手順
-

5年遠回りした「学習OS」の”心臓部”は、AIプロンプトだった。あなたの『分かったつもり』を破壊する「ログシバ式・学習OSプロンプト」【お試し版/完全版比較】
-

【2026年合格目標】5年目の凡人が追加投資5.5万円で挑む、診断士合格への全戦略
-

【診断士受験生へ】NotebookLMを知らないと損!僕の学習効率が5倍になった「学習OS」構築術
-

『これ、紙の方が速いじゃん…』- 僕がiPad miniでの大失敗から見つけた、最高の自己投資としてのiPad Pro/Air
【学習OS運用ログ Vol.3】「このままじゃ間に合わない…」焦るあなたへ。僕が”急がば回れ”と決めた理由

【序章】「進んでいる」はずなのに、なぜ「焦る」のだろうか
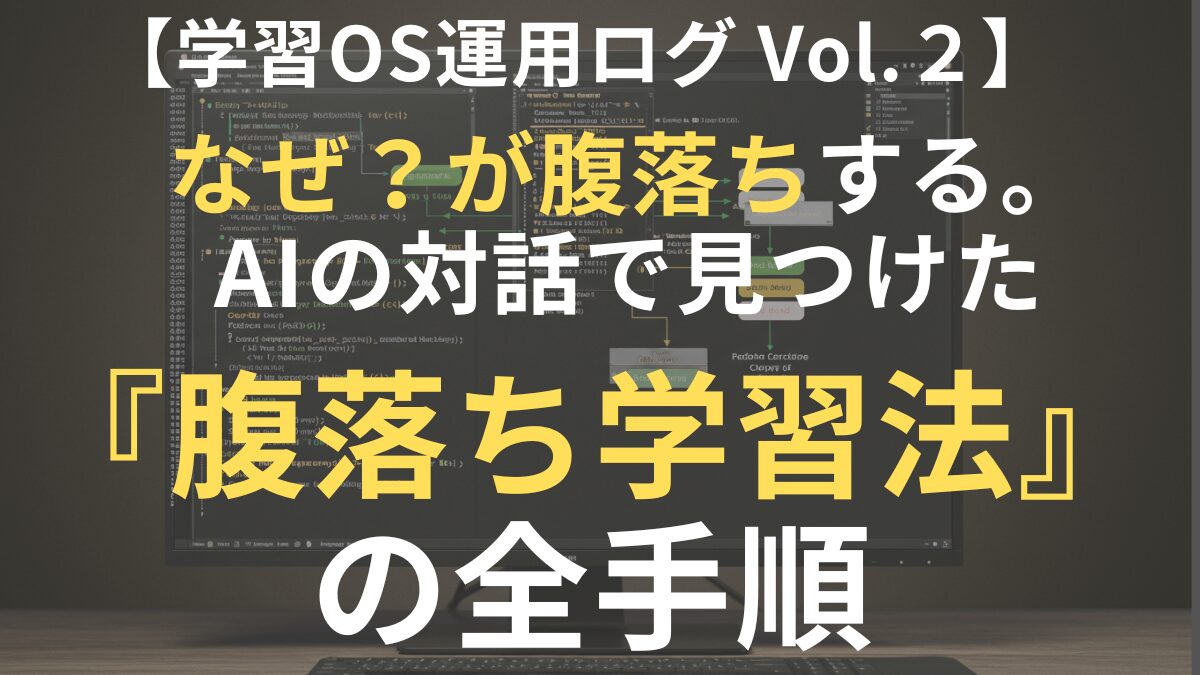
前回の記事で、AIとの壁打ちを重ねることで自分なりの「三重殺学習法」を確立した僕。あれから2週間、その手応えは確かなものでした。1問1問の知識が、ただの暗記ではなく、血肉に変わっていく感覚。過去の僕では決して見えなかった景色が、そこにはありました。
しかし、その一方で、僕は新たな壁にぶつかっていました。
「このペースで、本当に間に合うのか…?」
まるで、自分だけが時速30キロで高速道路を走っているような、じりじりとした焦り。周りの車が猛スピードで追い抜いていく幻覚さえ見えてくる。あなたも、学習の「深さ」と「速さ」という、決して交わらない二律背反のジレンマに、心をすり減らしてはいませんか?
この記事は、そんな僕が焦りのど真ん中で見つけ出した、自分を信じるための「心の処方箋」の物語です。
【Check】新たな壁 ― 「深く」と「速く」のジレンマ
僕の新しい学習法は、1問ごとにGeminiやNotebookLMに問いを投げかけ、完全に「腹落ち」するまで次に進まない、というものです。このおかげで、かつて僕を苦しめた「分からないまま進んで、結局何も身につかずに嫌気がさす」という最悪の負けパターンは、確実に回避できていました。
しかし、光が強ければ影もまた濃くなるもの。その代償は、あまりにも大きなものでした。
一日があっという間に溶けていくんです。朝から晩まで机にかじりついても、進むのはたったの6問か…。
1問1問の理解が深まる満足感と、カレンダーを見て感じる絶望的な遅れ。この矛盾した感情が、僕の心を少しずつ蝕んでいきました。テキストは全518ページあるのに、まだ128ページ。僕の学習計画は進まないどころか、このままでは試験範囲を網羅した後の「解き直しの時間」がなくなってしまうのではないか?
かといって、ここで焦ってスピードを上げるのはあまりに危険です。過去の僕は、まさにそれで失敗したのですから。
去年とか一昨年は、「とりあえず全部回らなきゃ」という意識があったから、分からないことを分からないままで済ませてしまった。そして、もう一回解き直したときには、本当に何も分からない状態で、それで嫌気がさしてしまったんです。
「深く、しかし遅い」今のやり方を信じるべきか。それとも「浅く、しかし速い」過去の失敗に再び身を投じるべきか。僕の心は、重たい振り子のように揺れていました。
【Action】光明を求めて ― ある会計士の時間術との出会い
朝の時間は確保できず、平日は往復2時間の通勤電車が唯一の聖域。土日は、一週間で散らかりきった家を「フルリセット」するための家事で一日が終わる。まさに社会人の勉強時間がないという悩みの典型です。そんな八方塞がりの状況で、僕にできることは多くありません。
わずかな昼休み、僕はワラにもすがる思いで、スマホでAmazon Primeの無料本を読み漁っていました。目次をざっと眺め、次に「終わりに」を読んで、著者の結論と考え方が自分に合うかを確認する。そして、ビビッときた部分だけをつまみ食いする。そんな我流の速読術の中で、僕はある一冊の本に吸い寄せられました。
弁護士であり、米国公認会計士でもある佐藤隆之さんの著書、『仕事と勉強を両立させる時間術』です。
【Action→Next Plan】僕のOSが更新された「2つの確信」
正直に告白します。この本を読んで、僕の心に最も深く突き刺さったのは、あまりにも当たり前の、しかし僕が完全に見失っていた一言でした。
確信①:「夜10時に寝る」という新ルール
「夜の1時間、2時間かけて勉強するぐらいなら、寝て、日中のパフォーマンスを高める」
著者はそう断言します。最近、睡眠不足で頭がボーッとして、簡単な計算ミスをしたり、危うく電車を乗り過ごしかけたりすることが続いていた僕にとって、それは頭をガツンと殴られたような衝撃でした。そうだ、僕が今すべきことは、精神論で夜更かしして机に向かうことじゃない。パフォーマンスを最大化するために、まず生活の土台、その根幹である「睡眠」を立て直すことだったんだ、と。
(※睡眠の重要性については、厚生労働省のe-ヘルスネットでも科学的根拠と共に解説されています。)
確信②:「ノートを作るな」という自己肯定
そして、もう一つ。僕の心を軽くしてくれた言葉があります。
「ノートをただ書くのではなく、読みながら考え、頭の中で理解する」
これこそ、僕が試行錯誤の末にたどり着いた『ログシバ式 学習OS』の思想そのものでした。
「僕のやり方は、間違っていなかったんだ」
この一冊の本は、僕に新しい知識を与えてくれただけではありません。僕が独りで歩んできた道が、確かにゴールに繋がっていると教えてくれる、心強い道標となったのです。
【学びの言語化】僕が掴んだ「焦らず、着実に進む」ための新ルール
今回の経験から、僕は自分の学習OSに3つのルールを書き加えました。
ルール1:進捗は「感覚」ではなく「数字」で見る
518ページ中128ページ。進捗率を計算してみると約25%。感覚的には「全然進んでいない」と焦っていましたが、数字で見ると「4分の1は終わっている」と冷静になれたのです。絶望するには早すぎるし、楽観するには心もとない。でも、これは紛れもない「事実」です。資格勉強の焦りから自分を守る最強の盾は、客観的な事実をおいて他にありません。
ルール2:「腹落ち」する理解を最優先する
スピードはその結果としてついてくるもの。もう、過去の失敗は繰り返さない。「自分でちゃんと腹落ちするように解かないといけない」。特に中小企業診断士の財務会計が苦手な僕にとっては、このプロセスを飛ばすことは自殺行為です。時間がかかっても「自分でちゃんと理解する」という今のプロセスを、何よりも大切にする。急がば回れ、です。
ルール3:最高のパフォーマンスは「睡眠」から
無理な夜更かしは、百害あって一利なし。日中の集中力を高めるため、「夜10時就寝」を新たなルールとしてOSに組み込む。これは根性論からの脱却であり、僕にとっての戦略的な休息です。今回の勉強法に関する本のおすすめポイントは、まさにこの「戦うための休息」という視点でした。
【結論】あなたの「焦り」の正体はなんですか?
計画通りに進まない焦りの中にこそ、現状を打破するヒントは隠されています。
僕にとってそれは「睡眠不足」と「進捗の可視化」でした。あなたにとって、それは何でしょうか?
もしよければ、あなたが勉強のスピードと理解の深さ、どちらを優先しているか、その理由もぜひコメントで教えてください。僕たちだけの「正解」を、一緒に探していきましょう。
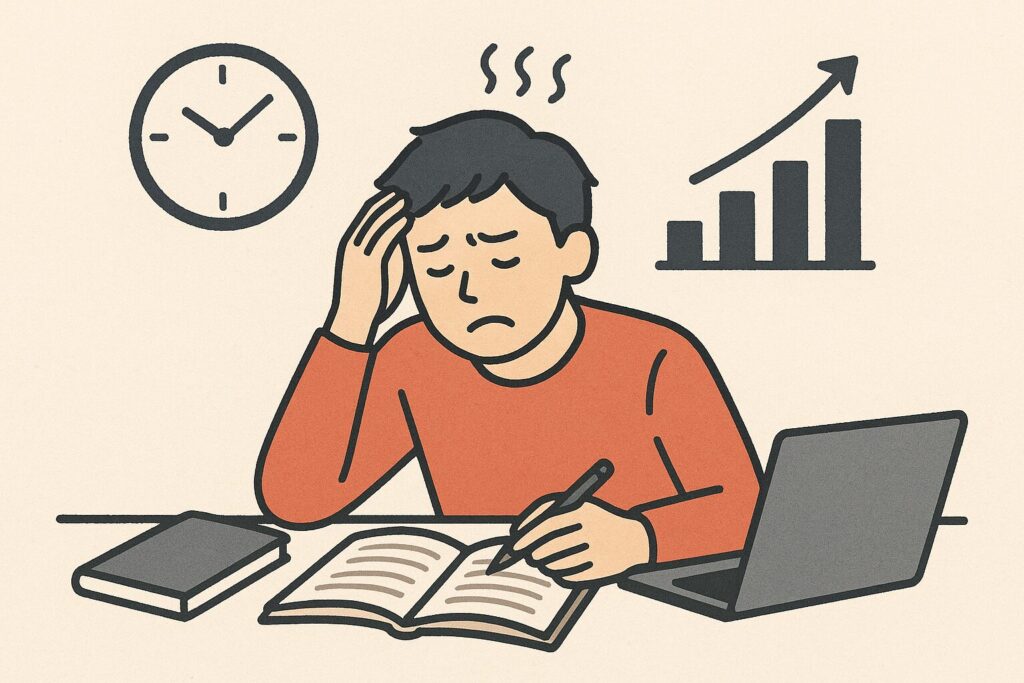

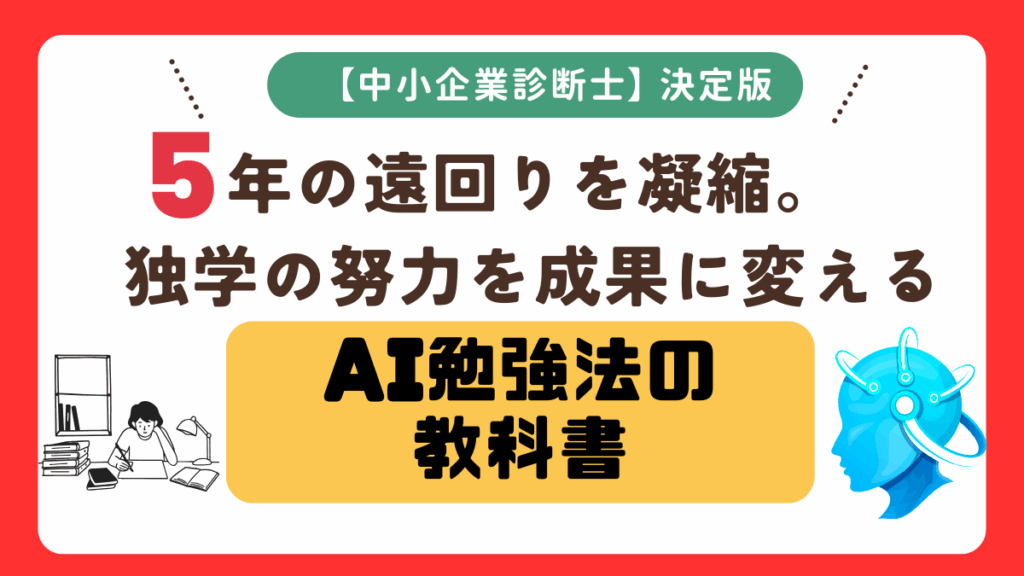
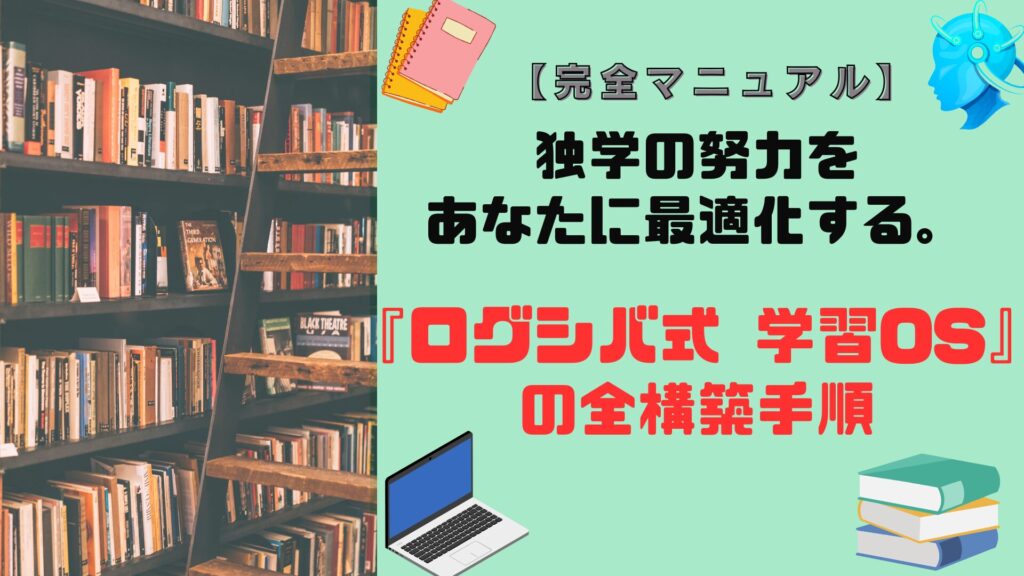
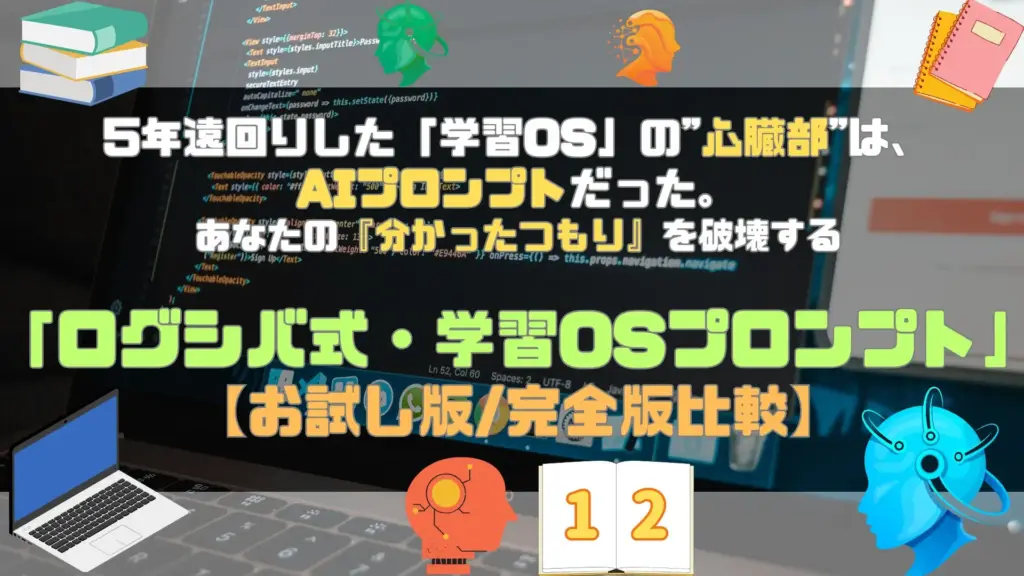
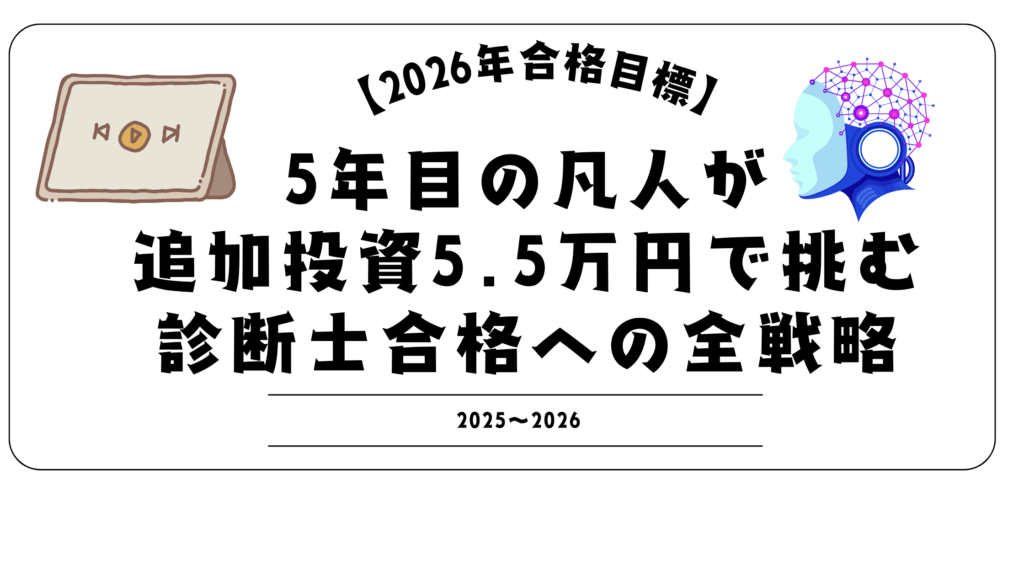
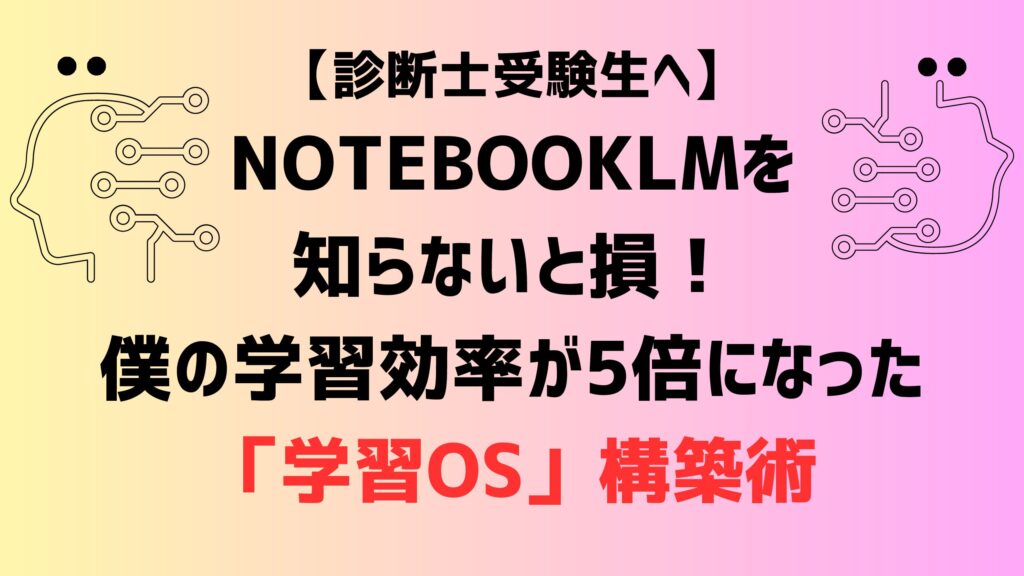
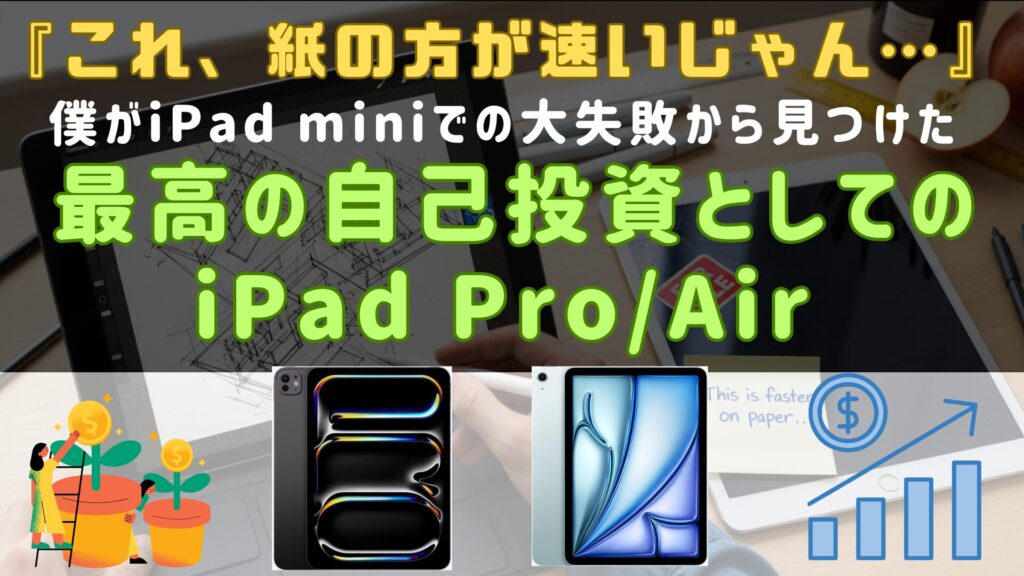

コメント