-

【中小企業診断士・決定版】5年の遠回りを凝縮。独学の努力を成果に変える『AI勉強法の教科書』
-

【完全マニュアル】独学の努力をあなたに最適化する。『ログシバ式 学習OS』の全構築手順
-

5年遠回りした「学習OS」の”心臓部”は、AIプロンプトだった。あなたの『分かったつもり』を破壊する「ログシバ式・学習OSプロンプト」【お試し版/完全版比較】
-

【2026年合格目標】5年目の凡人が追加投資5.5万円で挑む、診断士合格への全戦略
-

【診断士受験生へ】NotebookLMを知らないと損!僕の学習効率が5倍になった「学習OS」構築術
-

『これ、紙の方が速いじゃん…』- 僕がiPad miniでの大失敗から見つけた、最高の自己投資としてのiPad Pro/Air
コピペで終わらせない。『AIプロンプト設計図』-あなただけの最強の指示書を組み立てる全手順
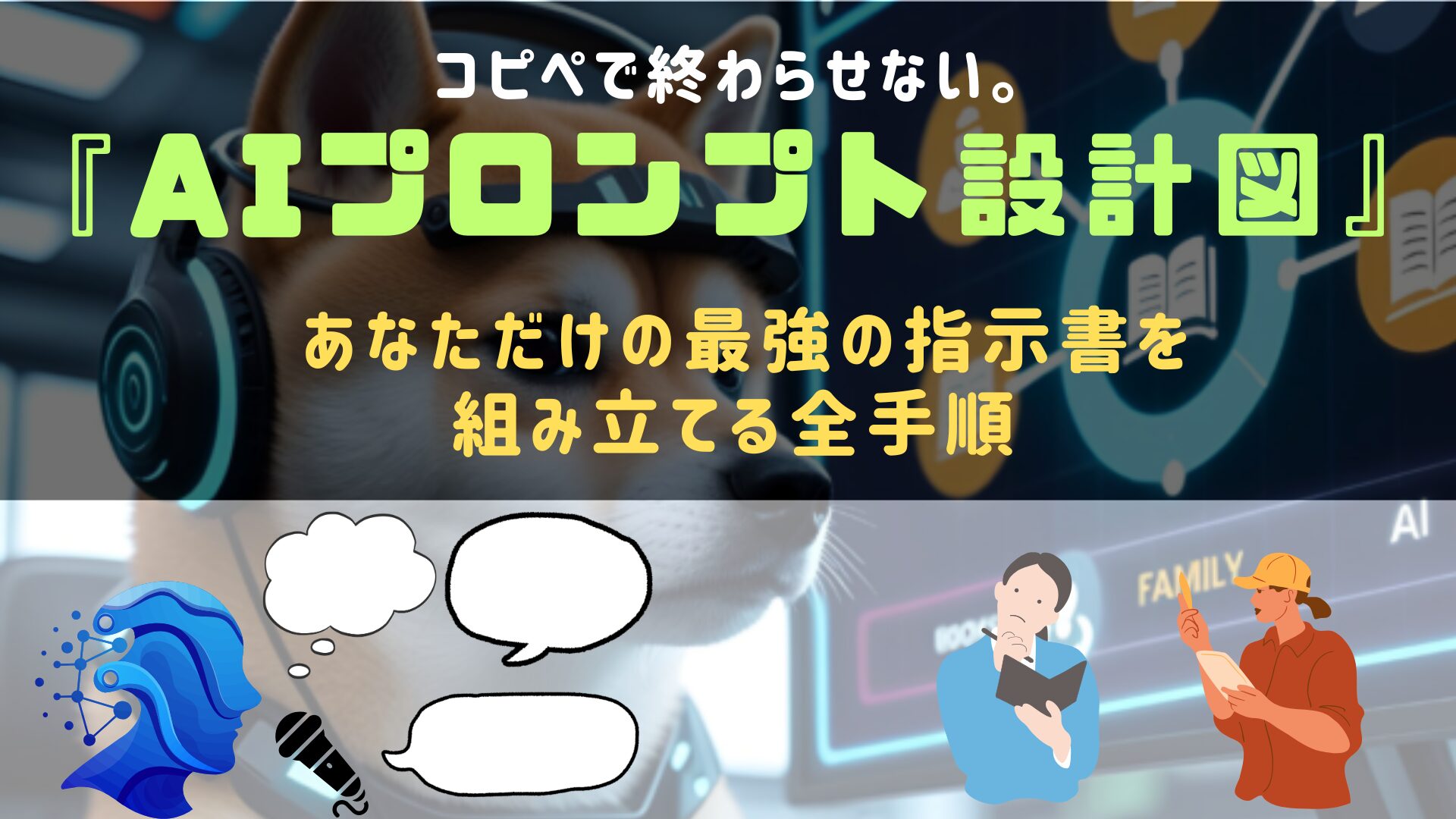
【序章】さあ、あなただけの「指示書」を作ろう
『AI勉強法の教科書』を読んで、「AIは新人だ」というマインドセットはもう完了しているはずです。
ここから先は、精神論ではありません。「技術」の時間です。
ネットに落ちているプロンプトをコピペするのは、もう終わりにしましょう。
あれは他人の課題を解決するためのもので、あなたの課題にはフィットしません。
この記事では、前回の記事で紹介した「4つのパーツ」を組み合わせ、あなたの学習課題を解決するためだけの「専用プロンプト」を、今ここでゼロから設計します。
読み終える頃には、あなたの手元に一生使える「マスターテンプレート」が完成していることを約束します。
準備はいいですか?
早速、組み立てに入りましょう。
まだ『教科書』を読んでいない方へ
AIへの指示がなぜうまくいかないのか?
その根本的な「考え方」を知りたい方は、まずこちらを先に読んでください。
👉 【中小企業診断士・決定版】5年の遠回りを凝縮。独学の努力を成果に変える『AI勉強法の教科書』
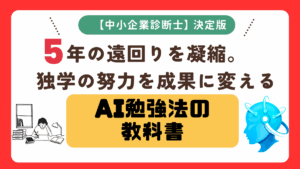
第1章:基本設計図(マスターテンプレート)
早速ですが、これが結論です。
あらゆる科目の、あらゆる質問に対応できる「万能の設計図」をここに用意しました。
まずはこれをコピーして、あなたのメモ帳(NotionやEvernote等)に貼り付けてください。
# AIへの指示書(マスターテンプレート)
## 1. 役割 (Role)
あなたは、私の[何の専門家]です。
(例:中小企業診断士のベテラン講師、戦略コンサルタント、辛口の編集者)
## 2. 前提条件 (Context)
* 私の目標:[最終的なゴール]
* 私の状況:[現在の理解度や悩み]
* この回答の用途:[何に使うか]
## 3. 具体的タスク (Task)
以下の【入力データ】について、[具体的な動詞]をしてください。
(例:小学生でも分かるように解説、メリット・デメリットを比較、誤りを指摘)
【入力データ】
(ここに質問したい内容や、過去問の文章などを貼り付ける)
## 4. 出力形式 (Format)
以下の形式を厳密に守って、回答を作成してください。
(例:会話形式で、表形式で、結論ファーストで、重要箇所を太字で)
このテンプレートは、僕が試行錯誤の末にたどり着いた「黄金比」です。
AIという新人は、この空欄([ ]の部分)さえ埋めてあれば、必ず期待以上の仕事をしてくれます。
第2章:【実演】テンプレートをどう埋めるのか?
「型は分かったけど、具体的にどう書けばいいの?」 そんな疑問に答えるために、実際に学習で使える「記入例」をお見せします。
例えば、「企業経営理論」の難解な文章が理解できない時、このように埋めて指示を出すことができます。
▼ 記入例:難解な理論を「腹落ち」させたい時
1. 役割
あなたは、「世界一わかりやすい解説」で定評のある人気予備校講師です。
2. 前提条件
私は独学で診断士を目指す初学者です。教科書の定義が抽象的すぎてイメージが湧かず、困っています。
3. 具体的タスク
以下の「リソース・ベースド・ビュー(RBV)」の定義について、「商店街の八百屋さん」を具体例に使って解説してください。
専門用語は使わず、なぜその理論が重要なのか、背景にあるストーリーを教えてください。
4. 出力形式
先生と生徒の「会話形式」で
重要なキーワードは太字で
どうでしょうか?
ここまで具体的に指示されれば、AIは「八百屋さん」という舞台設定の中で、RBV(内部資源)の話を生き生きと語り始めざるを得ません。 これが「設計」の力です。
「自分で作るのが面倒」な方へ
「理屈は分かったけど、毎回これを作るのは大変…」 「手っ取り早く、科目ごとの完成品が欲しい」
そんな効率重視の方のために、中小企業診断士試験の「全科目のプロンプト(完成版)」をまとめたNoteを用意しています。
今回紹介した「翻訳家モデル」や「アナリストモデル」はもちろん2次試験の事例Ⅰ〜Ⅳに対応した「自動添削プロンプト」など、磨き上げた「指示書のセット」です。
時間を節約したい方は、こちらを活用してください。
(※ワンコインのお試し版もあります)
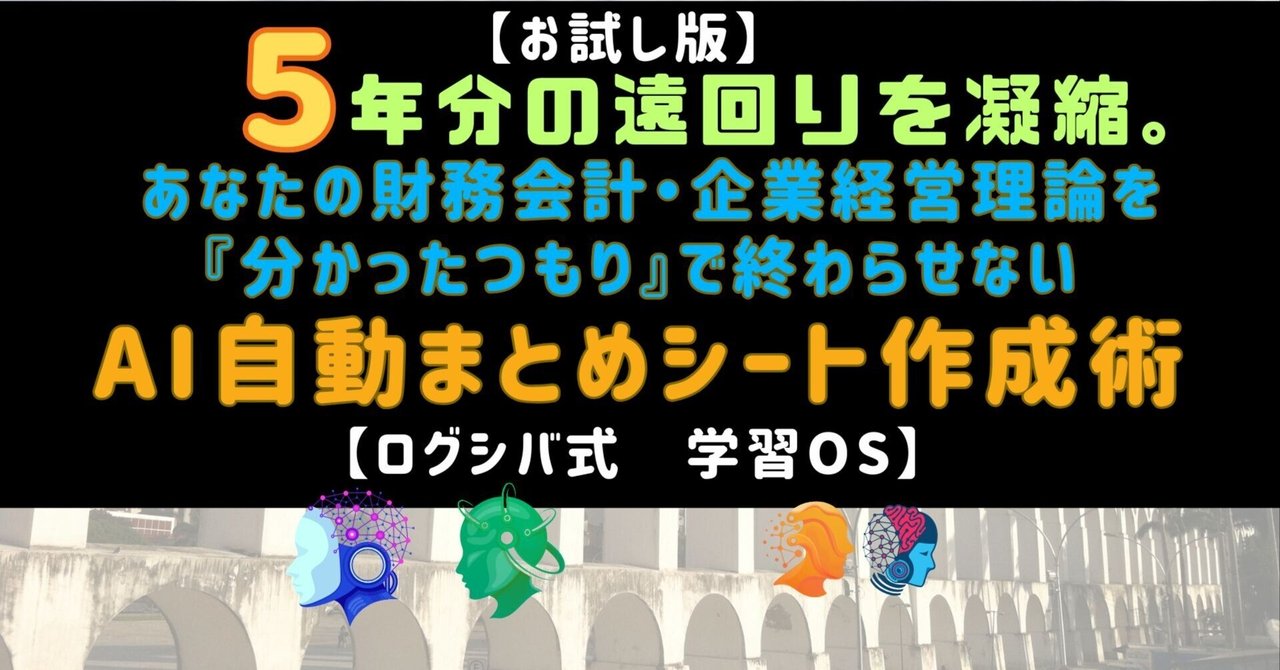
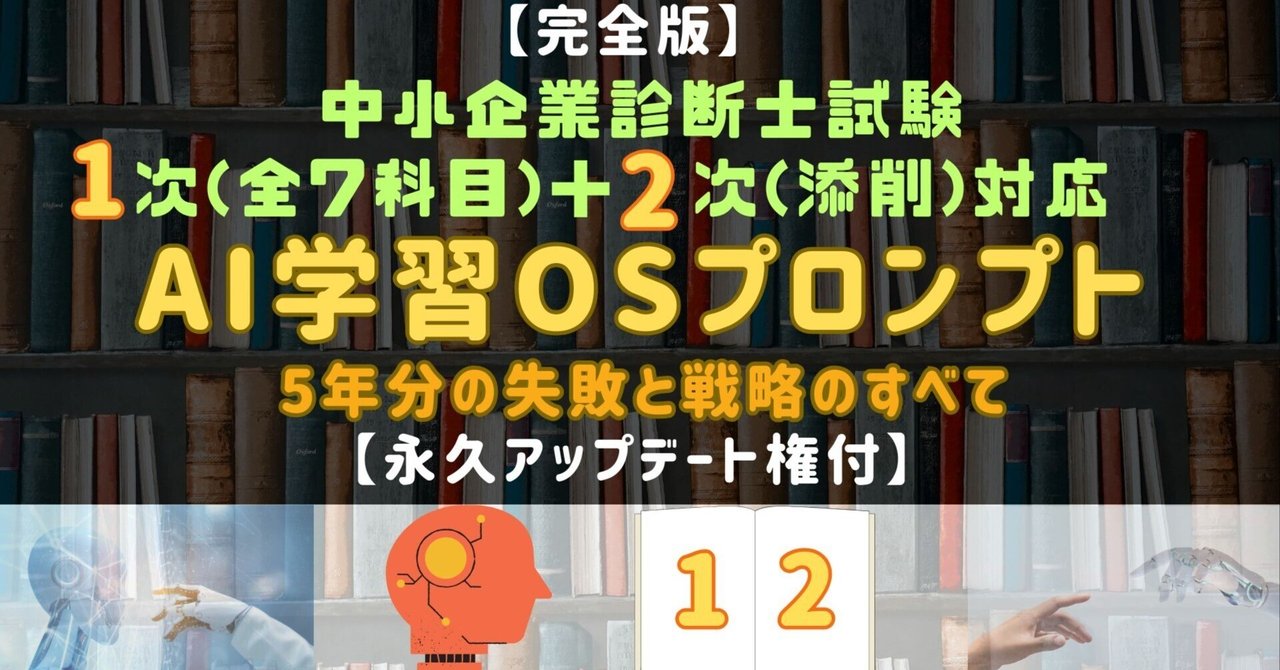
第3章:性能を極限まで高める「チューニング」
基本のテンプレートだけでも十分ですが、さらに回答の質を高めたい時に使える「オプションパーツ」を3つ紹介します。
テンプレートの好きな場所に追記して使ってください。
① 思考の抜け漏れを防ぐ
「ステップ・バイ・ステップで考えてください」
効果:
AIの「早とちり」を防ぎます。
複雑な計算問題や、論理的な分析を依頼する時、この一言があるだけで正答率が跳ね上がります。
② 客観的な視点を与える
「あえて批判的な視点から、私の考えの弱点を指摘してください」
効果:
2次試験の記述対策で有効です。
自分の解答に対して「イエスマン」にならず、採点官のような鋭いツッコミを引き出せます。
③ 出力のクオリティを固定する
「以下の【お手本】の文体と構成を真似して出力してください」
効果:
あなたが「分かりやすい!」と思った過去の解説文などを【お手本】として貼り付けると、AIはそのスタイルを完コピしてくれます。
④ 思考の限界を突破する
「常識にとらわれず、最も斬新で大胆なアイデアを3つ提案してください」
効果:
企業の改善案を考える時など、ありきたりな答えしか出ない時に使います。
AIのリミッターを外し、ハッとするような切り口を引き出せます。
⑤ 思考の焦点を絞らせる
「以下の長文をまず黙って要約し、その内容を完全に理解した上で、私の質問に答えてください」
効果:
長いWeb記事やPDFの内容を質問する時に必須です。
いきなり質問せず、一度「読み込み」の時間を強制的に与えることで、回答の的外れ感がなくなります。
第4章:設計図を手に入れた、次のアクション
これで、あなたは「AIへの指示」を自由に設計できるスキルを手に入れました。
しかし、スキルは使わなければ錆びつきます。
あなたの「現在の状況」と「確保できる時間」に合わせて、次に取るべきアクションを選んでください。
【ルートA】「作る時間」をお金で買って、学習に集中したい方へ
「設計方法は分かった。でも、今は1分でも多く勉強したい」
「プロンプト作成に悩む時間をゼロにしたい」
そんな方は、迷わず「完成品」を導入してください。
僕が5年かけて磨き上げた指示書セットを使えば、あなたは面倒な設計作業をスキップして、今すぐ「質の高い学習」だけを享受できます。
- お試し版(500円): 苦手な「財務・会計」「企業経営理論」に特化
- 完全版(3,980円): 全科目+2次試験+自動添削機能付き
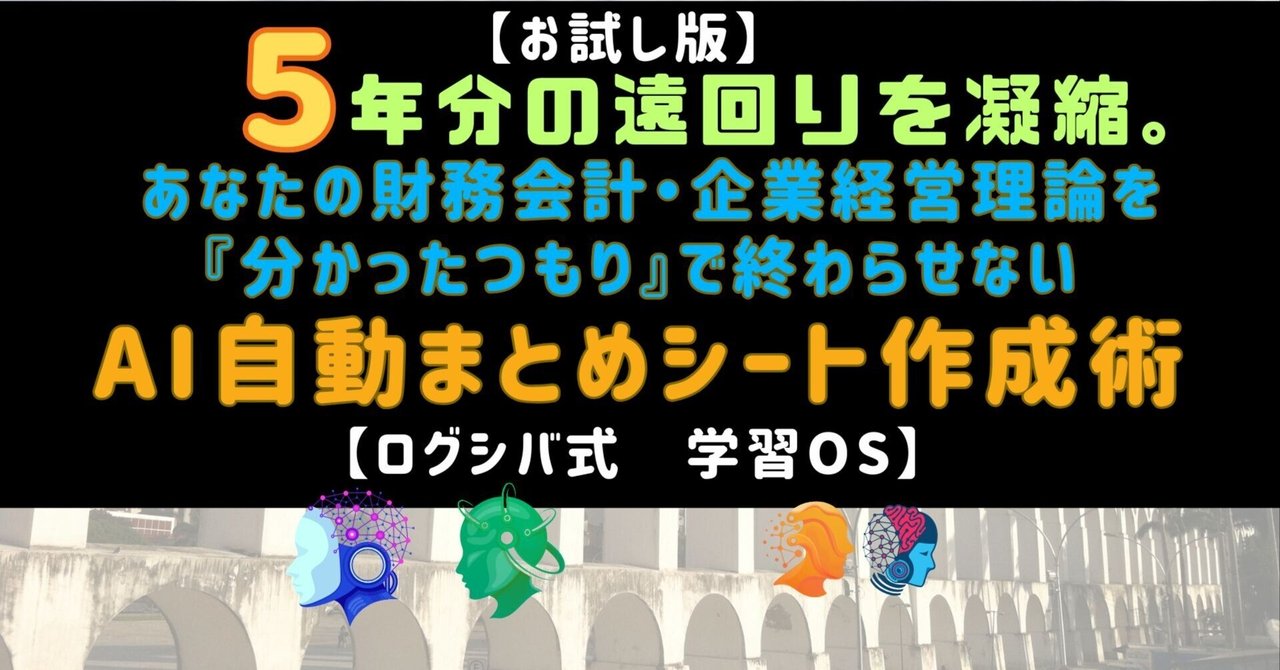
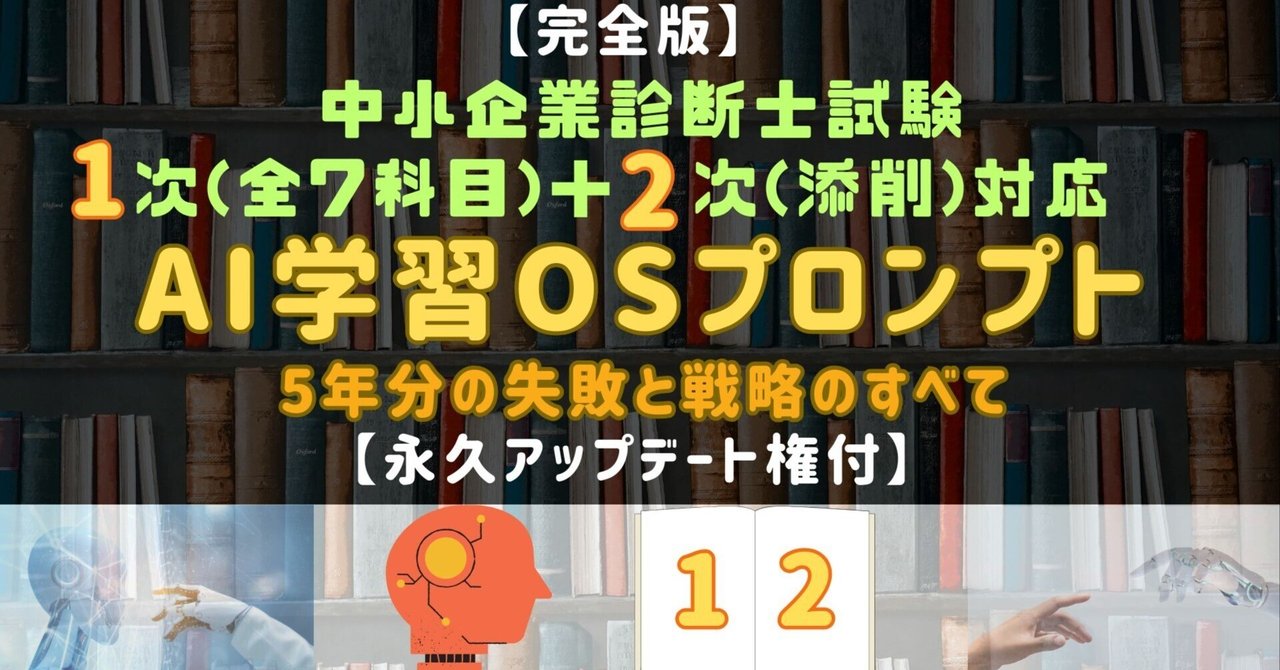
【ルートB】学習環境そのものを「自動化」したい方へ
「プロンプトだけでなく、テキストの整理や復習も効率化したい」
「iPadとAIを連携させた、最強の学習環境を作りたい」
そう感じる方は、『システム構築』のフェーズへ進んでください。
GeminiとNotebookLMを活用し、インプットからアウトプットまでの工程を半自動化する「ログシバ式 学習OS」の構築手順を解説しています。
👉 【完全マニュアル】独学の努力をあなたに最適化する。『ログシバ式 学習OS』の全構築手順
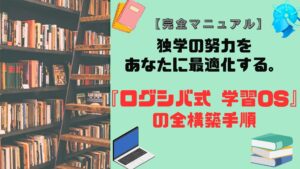
【ルートC】「計画倒れ」の原因を特定し、改善したい方へ
「便利なツールを知っても、継続できるか不安だ」
「いつも計画だけで終わってしまう」
もしそう感じるなら、ツールを使う前に『自己管理(PDCA)』の見直しが必要です。
なぜ計画が崩れてしまうのか。
その根本原因を3つのタイプで分析し、無理なく継続するための「自己分析手法」はこちらです。
👉 【PDCA勉強法】なぜ計画倒れに?自己分析で原因を見つける3つのステップ
(※ツールの前に、まず「あなた自身の行動」をマネジメントする方法論です)
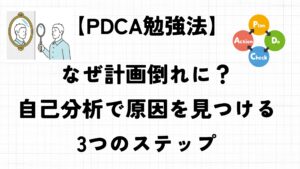
【さいごに】
設計図は渡しました。 あとは、あなたが実際に手を動かし、AIという新人に最初の指示を出すだけです。
まずは第1章のテンプレートをコピーし、あなたが今一番苦手な論点について、AIに質問してみてください。 返ってきた答えが、あなたの脳に「スッ」と入ってきた瞬間。それが、あなたが「AIの操縦者」になった瞬間です。
あなたの作ったプロンプトで、どんな成果が出たか。ぜひコメントで教えてください。 健闘を祈ります。

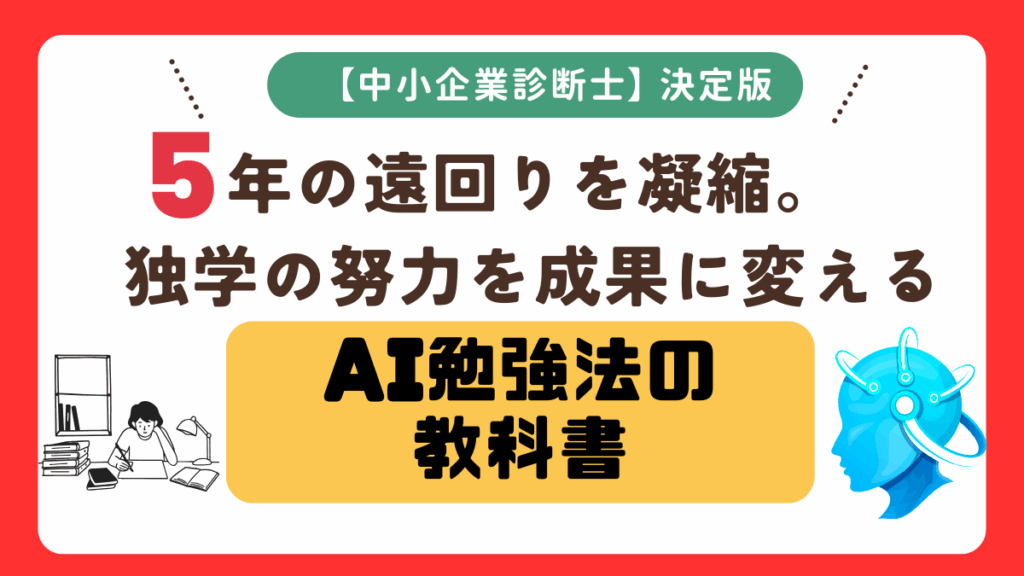
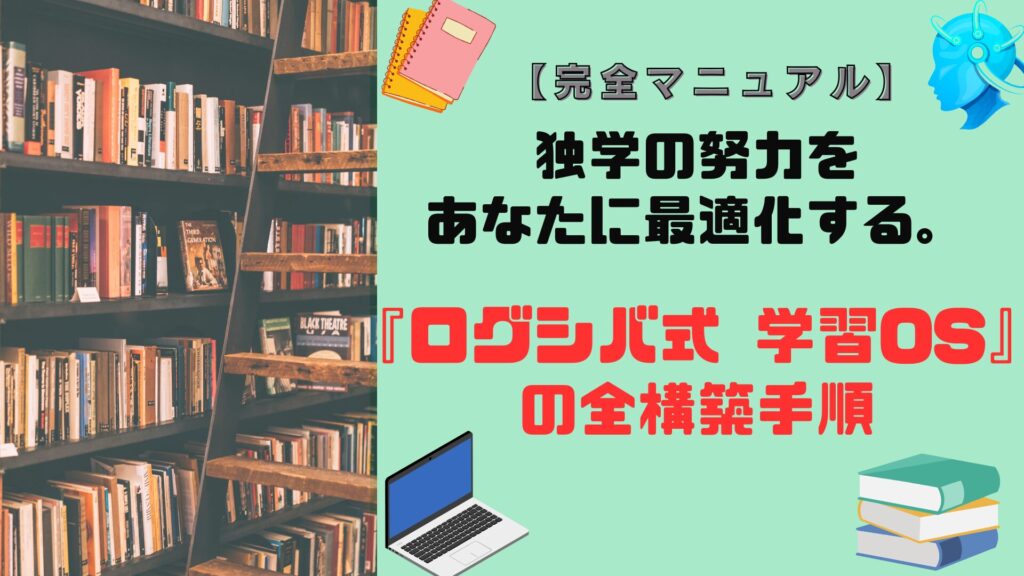
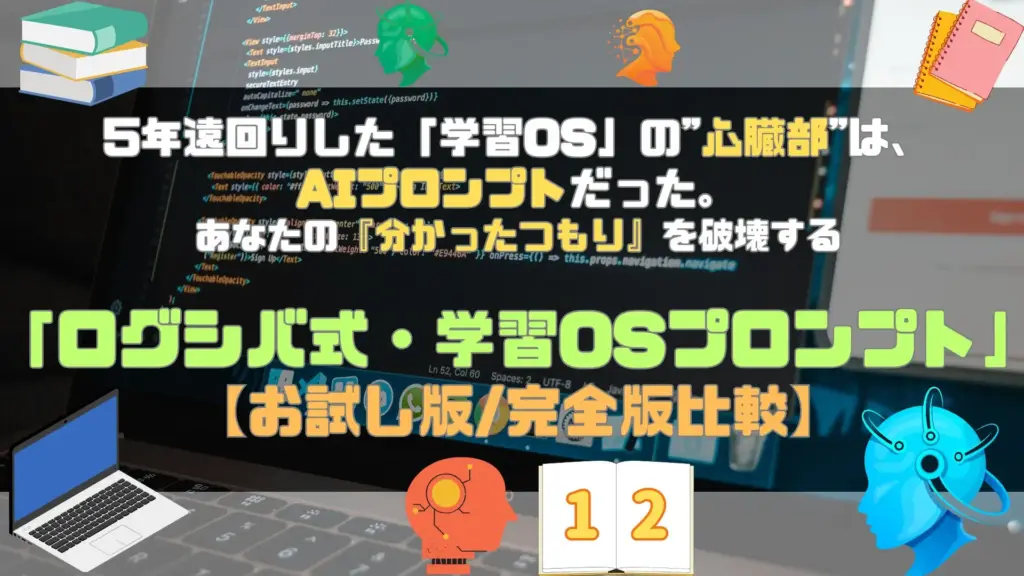
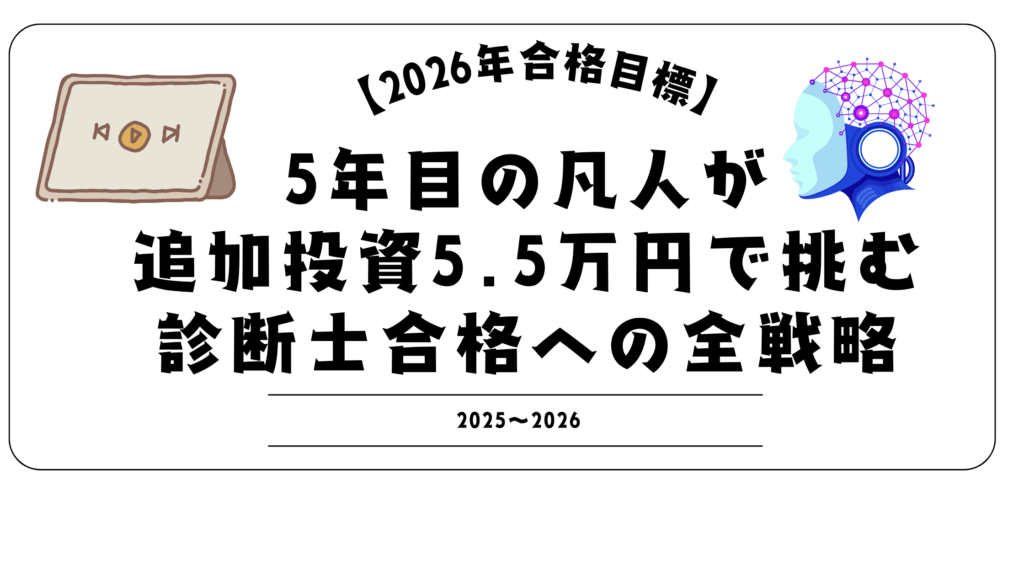
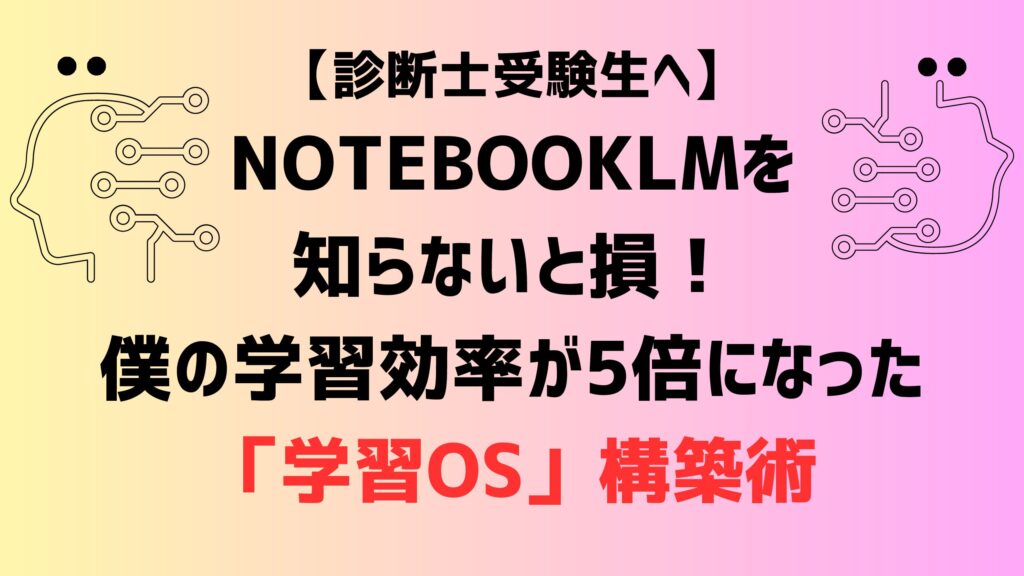
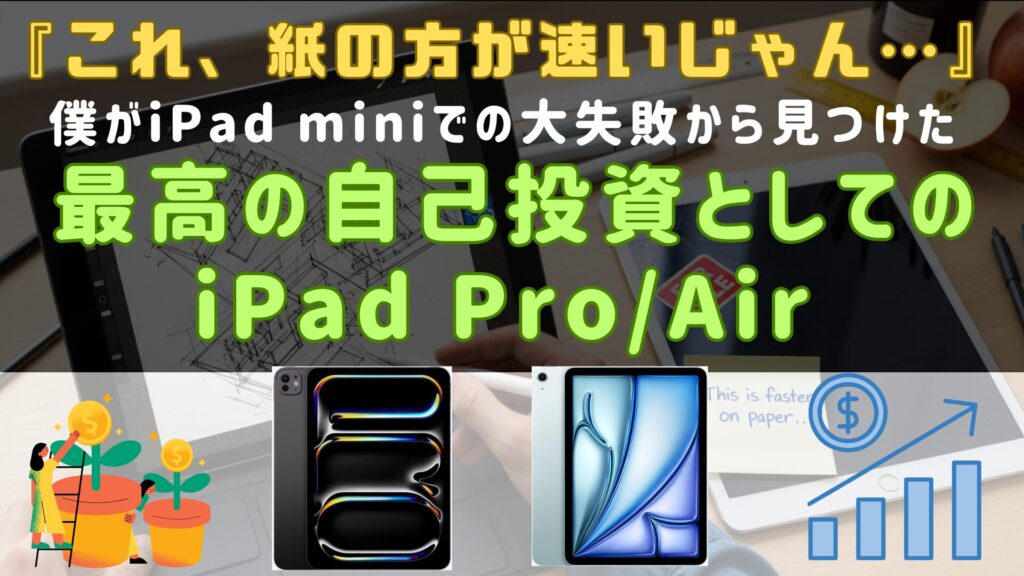
コメント